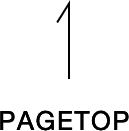vol.09 岩井 俊二 さん
小林武史が各界のゲストを招いてさまざまなテーマで語り合う対談連載。
今回のゲストは映画監督の岩井俊二さん。
盟友とも言えるふたりがコロナ禍のなかで語る現在・過去・未来とは。
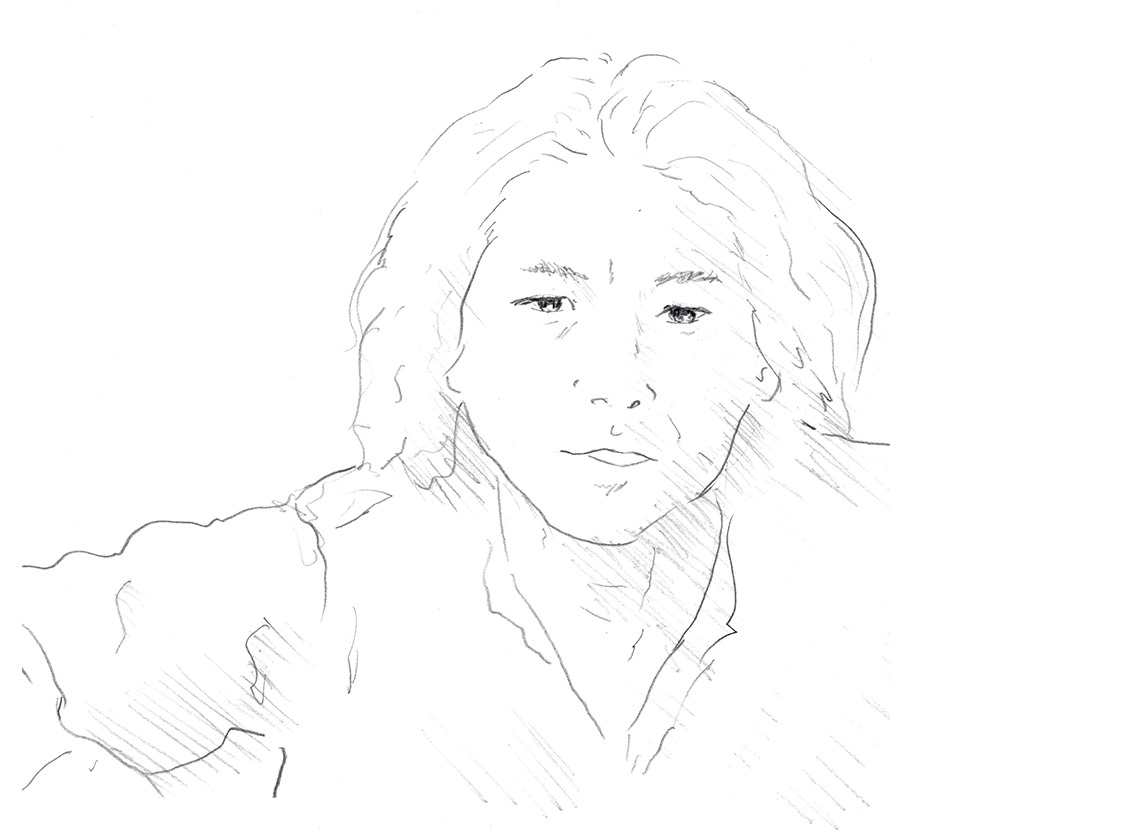
この10年ぐらい、ゆっくりではあるんですけど
微動だにしていないわけでもないという。
小林:ご無沙汰しています。『ラストレター』の打ち上げの時にちょっと行って、あれ以来。
岩井:あれ以来か。
小林:今年の1月。
岩井:コロナ以前ということですね。
小林:コロナ以前です。電話ではこのあいだ話したけど。
岩井:電話でちょっと話しました。
小林:大変な長丁場になろうとしているけれど。コロナのあたりの話もぜひいろいろ聞きたいんですけれども。震災があってもうじき10年ですけれども、あの時のことから振り返ってみられないかなと思ったんです。
岩井:震災の時、僕はロスにいて、たまたまスタッフと電話していたら、「大きな地震が来た」と電話越しに言われて、すぐテレビをつけて。向こうでNHKをやっているんですけど、すぐヘリコプターからの映像になって、程なくして津波が押し寄せてくる映像を見た記憶があるんですけど。そこに若林というテロップが出ていて。僕はまだ幼稚園に入る前でしたけど、そこのエリアに住んでいたことがあって。そこの町に津波が押し寄せていくのを見た衝撃が大きかったと思います。
地震よりもはるかに津波の被害がいまだに尾を引いていて。いずれ、何らかの形で表現しなきゃいけないかもしれない大きな課題のひとつとして、自分のふるさとを襲った津波というのが残っている気がします。
もうひとつ、福島第一原発事故に関しては、今もそうですけど、科学の進歩みたいなものに対して、人類はあまり抑制的ではなくて、ほとんどの場合、不用意にわれわれの生活に入ってきて、知らぬ間にとか、確証もないまま利用していって、結果、後戻りできないところに連れて行かれるケースが多くて。
そんな危機感から書いた小説があって、それが『番犬は庭を守る』という小説だったんですけど。
小林:それは、だいぶ前の話ですね。
岩井:そうですね。書いたのは2000年ごろだったんですけど。『リリイ・シュシュ』の前ぐらいに書いた話で。その当時、東海村の臨界事故というのがあって、作業員の方が亡くなった悲惨な事故があったんです。それと環境ホルモン問題というのが話題になっていた時期で。最近あまり言われないですけど、人間が出している化学物質が、微量でも胎児の成長なりに影響を与えるという理論だったんですけど。それで割と世の中が震え上がったという時期があって。性ホルモンに変異を来すみたいな。
その辺からイメージを広げて、科学の進歩とか、そういうものを受け入れ過ぎて、やや敗北してしまった世の中というか、ディストピアを舞台にした物語という。それでも生きていかなきゃいけないという宿命を抱えた人類、青年の物語でした。
それを書いておきながら、いろいろ経緯があって出版までたどり着かなくて。置き去りになっていたまま震災を迎えてしまって、原発事故を迎えてしまってという感じだった。そういうものを書いていながら置き去りにしていたということに、ちょっと罪深さを感じつつ。もともとチェルノブイリも見聞きしていた世代でもあるので。
決して安全とは思っていなかったところで、とうとう自分の国で事故が起きたという衝撃もありましたし。少し、ここで風向きが変わって、脱原発とか、そういうふうにシフトしてくれたらいいなという思いでした。そんな仲間が集まって「ロックの会」みたいになっていったと思います。
小林:ロックの会が5年ぐらい。
岩井:そのぐらいやっていましたね。
小林:最近は安倍さんが最後、有終の美みたいになってきちゃっています。
岩井:途端に支持率が上がったり、いろいろ。政権交代と言っても、次の方は当事者でしたから、何も変わらないんじゃないかということしか感じないですけど。
小林:僕からしてみれば、気候変動がダイナミズムをフルに発揮しながら、僕らに恐怖感と言っていいようなものを与えているのに、環境の「か」の字も問題としては出てこなくて。結局、大きな権力と仕組みの話を外から、自民党の中とか、派閥の力関係ということを論じるだけで、それでお腹いっぱいになっちゃっている。
僕らに語れる話は出てこないよね。安倍さんの国際外交力みたいな話がバンと出てきて。これからも安倍さんには活躍してもらわなきゃいけない、みたいなことが出てくるでしょう。
岩井:いろいろ不祥事があっても続いているわけですけど。あまり政治的なポリシーがないというのが、与党の強みなのかなという気がするんです。世の中のここを変えなきゃいけないというのがクリアにはっきりしてくると、その意見に対する違和感から内ゲバ的になって、だんだんバラバラになっているのが野党のような気がするので。そもそもそういうものを持っていない人たちが強いというか。
変な言い方をすると、「国民の政治的関心が薄れている」と言うんですけど、「政治家側の政治的関心が薄れている」という風になってきているような感じで。政局だけ見ているとややこしいんですけど。ただ、ポリシーがないので、希望的観測で言うと、これが問題だ、あれが問題だということが浮き彫りになれば、どこかが「え? そうなの?」ということになって、すぐにではないですけど、徐々に変わってくるというか。この10年ぐらいでも、LGBT問題とかいろいろ、ゆっくりではあるんですけど、微動だにしていないわけでもないという。
小林:そうだね。希望はある。ちょっとずつ良くなっているという感覚は、岩井くんも持ってはいる?
岩井:そうですね。本当はもうちょっと短期政権で動いたほうが、もうちょっと速いのかなというか、長期政権だと、動きがさらにスローになっちゃうだろうと思いつつ。政治的哲学とか、極端な思想に凝り固まられると、何も動かなくなると思うんですけど、そこに対してあまりポリシーがなさそうなところが、少し幸いかなという。結局、憲法にも指1本触れられなかったので。もっと強権的なのかなと思っていたけど、意外とそうでもなかったという印象はありますね。
小林:そうだよね。意外と、少年のころに誓ったおじいちゃんの夢をずっと追っていました、というレベルで終わっちゃったなという感じだった。
岩井:ただ逆に、戦略的にいろいろいじってしまった、例えば公文書を改ざんできるとか、小ずるいところというか、タチの悪いところはそのまま全部残っている気がするので。メディア統制とか、いろんなところの旨みは学習し切った政権でもあるので、そっちの不安のほうが大きいですかね。一番やってきた人が次の総理大臣になる感じなので、メディアとの間がどうなっていくのか、ちょっと心配ではありますけど。やり過ぎたと思うところが、いい方向に向かってくれることを祈るしかないです。あれはあれであまり良くなかった、ということを実感してもらえているといいですけど。
自分たちが損するのは嫌だという雰囲気が少しずつ変わってきた
小林:政治の話ばかりするつもりはまったくないけど、アメリカと中国の問題、中国の問題は香港とか台湾とかともつながっているし、岩井監督にしてみると、そこはホームグラウンドに近い問題でもあるし。
振り返ってみて、まさかアメリカにトランプ大統領みたいな存在ができるという予測は、僕がアメリカと行き来している時にはなかったんだけど。安倍さんのいろんな偽装問題でも、数の論理で押し切るみたいなことと同じものをトランプにも感じるし。
もちろん、もともと白人社会が、大航海時代とか植民地主義の時にやってきたことが反転して今、香港の人たちが逆に、トランプに「助けて」と言っているような不思議な、ねじれた現象を起こしている訳だけど。そのあたり、岩井くんはどういうふうにとらえています?
岩井:難しいですけど。僕ら、戦争でアメリカに負けて、その後、アメリカの傘下に入って、比較的アメリカの文化とか風俗に憧れを持ちながら暮らしていたと思うんです。
片方で、アメリカはいろんな所で戦争をやり尽くしている国でもあって。ベトナム戦争にしてもイラク戦争にしても、どの中東の紛争にもずっとかかわっているという。国内でたくさんの兵隊さんたちが死んでいるという、すごい国なんです。銃もOKだし。比較するとここまで狂暴な国は実はなくて。どこの国と見比べてもないんです。
片側で、そこにポイントがあると思うんです。中にいるのと外にいるのとで、だいぶ温度差があるというか。アメリカの外にいる人たちにとってのアメリカって、これほど恐ろしい国はなかったと思うんです。ほんとに攻めてくるので。戦争を仕掛けてくるので。いったん負けて傘下に入った日本にとっては、比較的穏やかに見える国というか。ハリウッド映画などが送られてくる、楽しいものが送られてきたり、ディズニーが送られてくるという国で、という。

それと比較すると、日本人のロシアとかアジアに対する恐ろしがり方は、これはこれで異色な感じはするんです。もっと恐ろしい国が太平洋の向こう側にいるのにというのは、なかなか日本人には実感できないというか。
僕の場合、映画を作りながら、アジアの国々のファンの人とも交流しているので、国の政策や何か、いろいろ各国あって大変ですけど、そこに住んでいる人たちは同じ人間であって、意外と文化も普通にシェアし合えている関係だと思うので。
そういう中で国同士が対立することは不幸なことだし、悲劇をもたらしていくので、あまり悪いほうに行かないようにしてほしいなと。市民レベルではどうにもならないところなので、分からないわけですけど。
その中で、市民レベルでやれることというと、文化的な交流とか、一緒にものを作ったりという中で、相手側の国とか、いろんな国の人たちの素顔を紹介していくというようなことが、少しでも平和活動につながるのかなと思ってやっている感じはあるんですけど。
小林:僕が岩井監督と最初に仕事をすることになったのは、間接的に桑田佳祐さんとかあるけれども、ちゃんとやったのは『スワロウテイル』で、YEN TOWN BANDだったりするわけだけど。
欧米の影響が湯水のように入ってくる中で僕らは成長してきたわけだし。一方で、戦争で日本は敗戦するけど、アジアの中ではその時の過程の中に傷跡というか、痛みみたいなものが残っているわけでしょう。僕らが加害者なんだけど。
その辺の背景も含めて、『スワロウテイル』を作っていく時のベースになった思いとか、振り返ると、どんな座標の中で、どういう思いで生まれてきたのか。
岩井:今思い返すと、最近の言葉で言うと「寛容でない世界」というのが、あの時代すでにあって。その当時も言っていたんですけど、当時の日本は、ある種の病院のような世界で。いろんな医療的な恩恵、医療っていうのは比喩ですけど、いろいろなサービスの恩恵を得ながら、そこに対するありがたみもあまりないまま、不満ばかりが噴出しているような世界というか。
それに対して、いろいろ厳しい環境の中で何とか暮らしている、海外から来た人たちの間にある連帯とか優しさとか強さとか、海外から知らない国にやってくるというバイタリティとか、そういうものに対する、それを失ってしまった社会に住んでいる側の憧れみたいなものが当時あったんです。
それは恐らくあまり変わっていなくて。いまだに、どうしちゃったんだろうと思うことがあります。例えばコロナでもそうでしたけど、感染した人をバッシングしたり、排除しようとしたりという、考えられないような真逆のことに転じていくというか。もうちょっと普通に、思いやりとか励ましとか、いろんなことがあっていいようなところで、非常にネガティブな意見が噴出したり。
『スワロウテイル』のちょっと前に『蟹缶』というショートドラマを作ったことがあるんですけど。
小林:『蟹缶』?初めて聞いた。
岩井:蟹の缶詰を盗まれたというだけの事件から、いろいろ尾ヒレが付いて、だんだん話がひどくなっていく男の話です。その中で、その当時は誇張して描いていたことがあって、でも今、ごく普通になった感じのことがあるんです。
蟹缶が盗まれたというのを「100万円盗まれた」みたいに言い替えて、警察も来るわ、ニュースでも取り上げられるわという状況になるんです。その後、床屋に行ってヒゲ剃ってもらっていると、横にいた同じ商店街の男が、「みんなに謝りに行ったほうがいいんじゃないか」となるんです。「え? 俺、別に悪いことしてないんだけど。俺、被害者だし」と。そうするとその男が、「おまえ、迷惑かけているんだよ。こんな騒ぎになっているじゃないか。このことについて商店街の各面々に謝りに行け」と言う場面です。
その当時、世の中がそうなっているつもりで書いていたわけではなくて、こんな言い掛かり言われたらたまらないよなというつもりで書いていたんです。でもその後、世の中で結構そういうのをあちこちで見るようになって、気がついたら、みんなが意味不明なところで、ひたすら謝罪する社会になってしまったという。
『蟹缶』を作ったのは1992年ぐらいだと思うんですけど、平成になりたてのころは、まだ謝罪の文化はなくて。それを僕が勝手に誇張して、そこは笑いのツボのところで、視聴者側からしたら、「そんなことで謝れる人いないよね」と、みんなワッハッハと笑えばいい場面だったのが、最近また観たんですけど、これ全然笑えなくなっているよなという。普通のことを言われているような状況になっていて。あれから日本の雰囲気も変わっちゃったんだなと。決していい方向に行ってない感じがするんです。
小林:ちょっとずつ良くなっているところもあるんだけれども。
岩井:あるけれど。
小林:米中とのやり取りとかもまったくそうだなと。普通に子どもみたいな言い掛かりのつけ方が、世界で起こっているでしょう。そういう悪い傾向がある。
でもアメリカ自体が、本当に攻めて行くということをずっとやっていたところから、トランプになってからもっとやりそうかと思っていたら、意外とビジネス的に、それは得にならないからということで、意外とやらなくなってきている傾向もある。
岩井:そうだよね。バブル期より明らかに良くなったこともあって。自分の記憶の中ですけど、バブルのころって、例えば環境問題に対しても、一般の若い子の認識で言えば、そういうこともあるけど、だからって自分たちの生活が削られるようなことは何ひとつしたくないよね、という世界でしたよね。
だからあのころって、エコバッグを使おうなんてことはあり得なかった世界じゃなかったですか? そこだけは退いてくれない感じが世の中にあって。自分の中でこれはお手上げだなと思っていたところが、今、みんなの意識は結構高くなって、世の中の役に立つんだったら少し自分たちの生活我慢しよう、というのはある種普通になってきているじゃないですか。あれは、バブル期にはまったくなかったですよね。
原発問題ひとつ取っても、自分たちの生活が1ミリでも損するんだったら嫌だというような雰囲気が主流だったので、果てしないなと思っていたんですけど、そこは少しずつ変わってきて、だいぶみんなの意識も、世代も代わる中で変わってきているんじゃないかと思います。
メッセージを実際に放ってきてくれた先輩たちがいる。
それが自分たちにも引き継がれていたりするのは
結構大事なこと。
小林:ところで、最新作、『8日で死んだ怪獣の12日の物語』、拝見させていただきましたけど、笑わせていただきました。すごくステキな映画だなと思いました。コンテンポラリーダンサー、すごくいいリズムで、いいムードをつくっているなと。
岩井:そうなんです。
小林:今コロナの時代に、そもそもどういういきさつで作ることになったのか。
岩井:最初に、『ガメラ』とか『シン・ゴジラ』の樋口真嗣監督とそのお仲間で、「カプセル怪獣計画」というリレー形式の、自分ちにある怪獣のフィギュアを使って、「おまえ、コロナと戦ってこい」みたいなことを言って画面にかざすと、次の人がリレーしていくというような、短い映像をつないでいくようなことを4月末から始めたんです。そのお誘いがこっちにも来て。うちに怪獣のフィギュアがなかったので、「自分で粘土とかで作ってもいいのか」と言ったら、いいということで。
ちょっと考えだしたら、卵からだんだん育てていったら面白いかなと思ってコンセプトから逸脱してしまって、樋口監督に「こういうショートストーリー考えちゃったんだけど、どう?」と言ったら、「それはそれで面白いからやりましょう」みたいになって。それで斎藤工さんに「出てもらえないかな」とお願いしたらOKだったので。まさに緊急事態宣言下で、LINEのやり取りで台本を送ったりして。
最初、YouTubeで12話に分けて配信して終わりにしようかというだけのものだったんです。斎藤さんしか出てこない設定だったんですけど。それはそれで、実際にYouTubeで5月に配信したんです。5月31日までの12日間で配信し切ったんですけど。それをやりながら、またアイデアがいろいろ浮かんでしまって、追加で台本をいろいろ書いていくうちに、だんだん膨らんでしまって、それも同時に撮りながら。
ほとんどは5月で撮り終わっていました。1時間くらいかなと思ってつないだら1時間半くらいになって。「これ、どこか映画館とかでかけてもいいかもしれないね」という話をプロデューサーとしていく中で、ちょうどミニシアターも今、大変な状況にあるので、少しでも応援できればということで。制作者側なので、劇場で公開されると制作者側の配当があるわけですけど、それを劇場に還元しようかということで、ミニシアター支援という形で公開まで進んだという企画だったんですけど。
なので、いつになく周到な台本の準備とか何もない、ほとんどアドリブ的な感じでことごとくやり切ってしまったので、こんなこともあるんだなと思いつつ。逆に言うと、プレッシャーもないところで、学生時代に撮った映画ぐらいの感じで自由に作らせてもらったので、久しぶりに、ただただ楽しんで作ってしまったというような感じでした。すごく趣味的なものでした。
小林:のんさんが、「見えない?ここにいるよ」というあのくだりからどんどん盛り上がっていくところが、すごく笑えた。「私も彼と一緒に行くのよ」という。あの辺で、どういう台詞だったか、「この星、全然駄目。いつまでたっても駄目」みたいなことを。
岩井:「人類ってこんなもの?」みたいな。「どうしちゃったの? 人類」とか。
小林:笑いながら、結構。斎藤工くんも、「ほんとにごもっともですけど」って、反論できないでいる感じも。笑いながらなんだけど的を射ていて面白いなと。
岩井:ノルウェーのグレタちゃんでしたっけ。
小林:グレタちゃん、スウェーデン。
岩井:スウェーデンのグレタちゃんをちょっとイメージしながら。最近この世に生まれてきた人たちにとっては、本当に、「いい加減にしろ、大人たち」というのがあると思うんです。いつの時代もそうかもしれないですけど、「何やってんだ、大人たち」というのは、若い子たちほどあると思うので。そこを、のんちゃんに言わせたかった感じはあります。

小林:無理なく笑いながらだけど、すごく効果的になっています。
岩井:そうなんです。僕もやりながらそう思いました。意外と的を突いているというか、真実を突いているんだよなというのは思いました。そこを目掛けたわけではないんですけど、のんちゃんのキャラクターを書いていったら、自然にあの台詞までたどり着いたという感じでした。
小林:今聞いてなるほどと思ったんだけど、最初は工くんのがいろいろYouTubeであって、後半もう1個膨らんで出てくる感じなんだね。
岩井:そうですね。
小林:樋口さんとか見ていると分かるけど、怪獣世代というか。いまだにどこかでそういうものを引きずっている奥には、宮崎駿さんとかもそうだと思うけど、手塚治虫さんとか。原子力の平和利用があったり。もちろんその前に、原爆を2個所で投下されたという原爆投下国としての、世界でもほかに例がない経験を通して、そこから活かしてきた戦後というのがあると思う。
僕はそれを、『ウルトラQ』でも『ウルトラマン』でも『ゴジラ』でも、楽しみながら育ってきたところはあるんだけれど。そういう日本のクリエイティブな流れというものって、岩井監督はどんなふうにとらえているんだろうなと。福島の事故も10年前に起こるわけですが。
岩井:僕は子どものころ、『ウルトラマン』や『ウルトラセブン』を観ても、多分、怪獣にしか目が行ってなくて、怪獣とウルトラマンが戦っている姿とか、そこしか観てなかった気がするんです。ただ、大人たちというか、制作者側はそこにいろんなメッセージを仕込んでいて、繰り返し観ていくうちにだんだん気づき出すんです。
そういう意味では、脚本家だったり演出家だったりが、子ども向けの番組を使って届けようとしたメッセージみたいなことって、どこか、子どもに向けているんだからというのではなくて、その子どもたちが大人になっても見続けるかもしれないからというところだったり、大人も一緒に観ているからという目線だったり。これって、意外と引き継がれているなというのは結構あって。
このあいだ終わった仮面ライダーシリーズがあるんですけど、これが結構大人向けで。たまたま観ちゃったらはまってしまって。企業買収とかM&Aみたいな言葉まで平気で出てきて。
小林:『仮面ライダー』にM&Aが出てくる?
岩井:出てくるんです。敵である大企業の社長と戦うんです、仮面ライダー同志で。バトルでは勝つんだけど、社会の力関係では依然敵が勝っているんです。子どもが観ていたのでは分からないというか、「今こっちが勝ったよね」という。毎回敵が負けて帰るんだけど、莫大な資産があって、まったく負けたうちに入らない。また毎週やって来るみたいな。状況は全然良くならない。こんなヒーローもの、初めて観たなという。
作っている人たちが結構ちゃんよく分かっている人たちで、子どもにはバトルを見せているけど、ドラマ自体は一緒にいる大人に向かって発信していて。
モノを作る側が世の中に対してやれることは少ないんですけど、そんな中でも、大人に対してのみじゃなくて、大人も子どもも含んだメッセージを実際に放ってきてくれた先輩たちがいて。それは意外とバカにならず、自分たちにも引き継がれていたりするので、そこは結構大事で。しっかり引き継いで、時代に即した新しいものをちゃんと発信しているんだなと思って、感心したんですけど。
小林:そうだよね。
岩井:仮面ライダーが中小企業の社長をやっているというのはすごかったですけど。
最初にも言いましたが、これから新しい科学技術がどんどん入ってくるので、すでにスマートフォンが5Gになってとか、いろんなものが入ってきて、便利だからつい使っていくんだけど、大丈夫なのかなという検証はなかなかされないままなので、どっちかと言うと、そっちのほうが怖い気がしているんですけど。
一部の人間だけがモノを持って、
困っている人たちを放っておいていたって
必ずそのツケみたいなものは回ってくると思う。
小林:でも今、考えていたんだけど、仮面ライダーの中に企業買収とか入ってくるって、資本主義の構造みたいなものが、かなり一杯一杯になっているのではないかと思います。だから分かりやすく善と悪に分けて。悪はそう簡単に滅びないというか、資本主義が滅びた先もまだ見えないから。
半沢直樹でも、ザックリ何となく観ていると、水戸黄門張りの勧善懲悪みたいな感じの雰囲気にはなっていて、金融資本主義の仕組み自体に、解説しながら物語を展開しているのも、デジタルインフラも含めて、かなり一杯一杯のところまで来ているから。そんな時代背景だから、子どもの番組の中にもそういうものを取り込んでいくような傾向が出ているのかと、話を聞いて。
もちろん、テクノロジーの問題のほうが、そこの中で自殺する子だって出てきているし、いろいろな弊害も何とかしなくちゃいけないというところまで来ていると思うけど。『NewsPicks』とかを観ていても、新しいビジネスの突破口みたいな話をしているけれど、どういう風に響いているのかなという感じもするんだけど。
岩井:そうですね。大きく様子が変わってはきていて。平成元年のころと平成30年ころの世界の各企業の資産価値を比較する資料があって、平成元年のころは日本の企業がベスト30の中に結構入っているんです。その当時、NTTが筆頭でしたけど。それが平成の最後のころになると、30位に入っているのがトヨタ1社で、しかもの最後のほうくらいでという。
それだけ見ると、日本がすごく後退したような印象ですけど、額面を見ると、トヨタも平成の最初のころより資産価値は上がっていて。それ以上にほかの企業がベスト30を席巻しているんです。その企業は30年前にはなかった企業ばかりで。GoogleだとかAmazonだとか、IT系だったり、アメリカだったり中国だったりというのが入ってきている中で、数字だけ見ると、日本は30年前とほとんど変わってないんです。
変わってないのが問題だと思うんです。別に落ちたわけでもないというか、ガラッと様変わりした市場のあり方みたいなところを、うまく乗り切れてないのがよく分かるわけです。そこに食い込んでくる日本の優良なIT企業がないという状況でもあって。そこは大きな問題だろうと思いつつ、世界がすごく変わってしまったというところも、ひとつの問題で。
そうなっていった時、今まで普通にあった、あって当たり前だった企業がどんどん用がなくなってしまったりするし。音楽業界も映像業界も、いろんな形で、それによって姿を変えさせられているというか。サブスクリプション的なものとかも、作り手のニーズから出てきているものじゃなくて、インフラから先に用意されて、そこに連れて行かれて仕分けされている、みたいな状況ですよね。
さらに今コロナでなおさら、あって当たり前だったいろんな仕事や風景が、また失われていくということが加速するというか。
そうすると、個人的に、SF的に考えた時の仮説があるんですけど、いずれ、クラウドを中心としたIT世界の中で社会主義のようになっていって、そういう企業がサービスを提供して、ほとんどのものはタダで手に入れてしまうという。ユーザー側の仕事もなくなってきて、労働と対価が見合わなくなっていって、結局そのバランスが崩れていく中で、みんながベーシックインカムみたいなものをもらって、最終的には、お金を得るために働くみたいなことが崩壊するんじゃないかという気がしているんですけど。
小林:僕もそれはすごく思っているんだけど。岩井くん的に言うと、ちょっと悲観的な気配があるのかなと。
岩井:あまりにも価値観が違うので、それを謳歌できるのか。昭和世代からすると、働く生きがいってあったじゃないですか。必ずしも、お金を稼ぐためだけに仕事していたわけではもちろんないわけで。ただ、そこに完全に紐づいた中での活動をさせられてきた側にとって、そこは、直接はもう関係ないんですとなった時に、どうなるんだろうという。じゃあ明日やればいいや、みたいな雰囲気になりはしないのかなとか、世知辛いところを心配するんですけど。
小林:確かに、締切りとかが近づくと、火事場の馬鹿力みたいなことってあるからね。
岩井:そうなんですよね。小林さんは、そこは割とポジティブですか?
小林:ずっとポジティブにとらえていたかも。
岩井:昔の手塚治虫さんとか、あのSFの世界で考えると、ロボットとかコンピュータの世界になって、労働のほとんどは彼らがやってくれるから、その分、人間は楽しく過ごせるというビジョンがありましたね。
小林:そうかもしれない。そうだっけ?
岩井:そうなんです。それはそうですよね。だって、それまで人が働いていたものをロボットが代わりにやってくれる。初めてロボットが小説の中に登場した物語があるんですけど、それも結局そういうものでしたから。人の代わりにロボットが働いてくれる世界。
ということは、その恩恵を人間が得ないといけないんですけど、現時点では成功した企業が独占していて。消費者としてはあるんですけど、リザーブされた労働分が自分たちに返ってくるというか。ロボットがすごく働いてくれているのに、人間は1日2時間くらい働けばもう大丈夫ですよ、とは全然なってないわけで。働く側にちゃんと下りてきてない状態で詰まっているような感じはする。
小林:でも、さっき社会主義的になると言ったけど、僕はある程度、資本主義に限界が来ていると。露骨に格差社会になってきているし、労働ということ自体が変わってきているし、そもそも今のIT業界の隆盛って、人がどれだけ動くかということじゃないところでお金が回っている。
その上で、世界の中のある種の倫理観として、デジタルのプラットフォームを最初に作った人たち、Googleにしても何にしても、ある程度利益を取ったら、公共性というところにシフトしていかないと駄目なんじゃないかという考え方に、共感しているし、そうなるべきだと思っているけど。
そうなっていくことで、もっとシェアしていくという感覚が生まれてくるだろうし。サステナビリティのことを考えたら、一部の人間だけがモノを持って、困っている人たちを放っておいていたって、必ずそのツケみたいなものは回ってくると思うので。利己的に考えても。
この対談のタイトルもそうだけど「利他のセンス」というような、全体からも見ていくということが、今、気候変動みたいに国境とか、コロナもまったくそうですけれども、国とか民族で限定できない問題として、そこを僕らは背負っていかなくちゃいけないという局面に来ているんだなという思いがある。デジタルのインフラもそういうふうに変わっていくべきだとは思っています。
でも、だからと言って、個人の中の生きることに対しての興味とか、競争原理みたいな。競争して面白いとか。競争して面白いというか、あいつよりももっといい曲を作りたいとか。単純だけど。そういう思いって、特に若い世代の中で消えたりはしないと思うけど。締切りに対してちょっとゆっくり、のんびりするところはあるかもしれないけど。
岩井:のんびりできるんだったら、それはそれで。今までせわしなくやって来すぎてもいたので、そこが良くなってくれればいいと思うので。今までかなり自然に対しても乱暴にやってきた社会から、一歩また優しい社会に向かっている気がするんです。あまりそこに負荷を掛けない世の中を世界中が求め始めているんでしょうし。
とはいえ、これだけは変わらないよなと思っていたのが移動なんです。流通だったり。これがコロナで止まったんです。これは唯一、去年まで人類が不可能だと思っていたことでした。止まったとしても再開すればまた元に戻るんですけど。ただ、止まったという状況に対して、どう社会を再構築するかということが、ある程度なされてから元へ戻ると、多分、前ほど激しい流通ではないような気がするんです。世界中のあらゆるものがどこへ行っても手に入るみたいな状況から、一歩冷静になって、できるだけ地産地消的なところに向かって、「でも、やっぱりいいよね」というようになってくれると、少しそこのカロリーは減るかなという気がするんです。
小林:それもすごく大事なことだと思うけど。何でも手に入るというのは、もっともっと、もっと距離を縮めよう、もっと時間を縮めようということから、1回コロナで、それができないとなった社会は、ものすごく気づかせてくれたものがあったと思う。
岩井:そうなんです。
小林:全体的にはすごく混沌としているけれども。アクセルとブレーキを両方踏む運転ですよと、急に言っても誰も、正しいアクセルとブレーキの同時の踏み方って、習っていないから。世界的に四苦八苦しながらやっているところはあると思うけど。でも、いろんなことに気づけてきている。
2000年にミレニアム憲章としてMGDsというのを出しているんだけど、その当時は誰も見向きもしていなかったんだけど。リーマンショックを経て、ESG投資というEnvironment、Social、Governanceという、人権とか環境とか統治していく力とかいうことも、全体のバランスとして企業をちゃんと判断しましょうよというものが、金融業界にもはっきり、ヨーロッパで出てきたというのがあって。日本もSDGsからはどこの企業もこれからは避けて通れないのではないかなと。どこかで全体がつながっているというのは、ちょっと考えればみんな分かることだと思うので。
そういう流れに、コロナが来て混沌として、利他どころではないなと思っていたけれど、結局は、利己的なことだけではどうにも解決できない。
宇宙時間のスケールからしてみたら
もう少しでいろんなことが変わっていく可能性を
持っていると思う
小林:最初の話に戻るけれども、あと数カ月で東北の震災から10年になろうとする。振り返ってみると、あそこには利他が、東北が持っている何かが、関係しているかもしれないけど、震災後そういう思いが増えていった。
僕も岩井くんも東北の出身ですが、東北には宮沢賢治という人がいて、利他というところで僕は賢治を思いだすんだけど。宮沢賢治は何年に死んだんでしたっけ。
岩井:1933年ですね、亡くなったの。終戦のちょっと前ぐらいですね。
小林:去年、「リボーンアート・フェスティバル」で、中沢新一さんが脚本を書いて、僕が音楽を作ったオペラで『四次元の賢治』というのがあったんです。なんと宮沢賢治を主人公にした物語だったんですけれど、法華経や仏教の影響にキリスト教も混じりそこに自然科学も加わった独特の世界観でした。
最後に宮沢賢治から話を展開できたらと思います。そもそも岩井くんは、どこか仏教と離れた宮沢賢治のことを話していたっけ。立ち話でこのあいだオペラを見に来てくれたときに聞いたような気がしたんだけど。

岩井:どうでしたかね。でも、仏教的宗教観の中にいた人なんだろうというのは、昔から意識はしていましたけど。すごく宗教的な内容が多いですよね。
小林:晩年の『銀河』とかは、キリスト教的な色合いがすごく強くなるという。音楽の世界でも、宮沢賢治という人が与えた影響というのは、いろんなところにあると僕は思ってます。
岩井:中学校くらいから、ずっと好きで読んでいますから。『銀河鉄道の夜』は自分のバイブルみたいな感じで。10代のころ、毎年のように読んでいた記憶がありますけど。宗教的というより、人の心に宿る信仰心みたいな部分にすごく関心があった気がします。宗教全体というより、人間が力及ばないところで何かに向かって祈るような思いだとか、そういうことに惹かれていたんだろうという気がします。
小林:本当にそうで。僕も、別に宮沢賢治のマネをしたわけじゃないけど、しかも毎日畑に入って鍬を入れているなんてことは全然してないけど、農業法人の代表をやっているでしょう。自然の力を使いながらやる営みをやっているけれど、自然と触れ合っているだけで、自然というのは、ある種、際限なく宇宙とつながっていくという思いがあって。常々、宇宙の一端にいるんだと。
でも人間の理解が及ばないことを想像力の中で補填していく、埋めていくというところに創作活動、クリエイティブがあると思うんです。
一方で、自然科学というものに目をこらしたり、耳を傾けるというか。そういうことの両面を持って生きていくというあり方みたいなもの。
それと、現代アートの方で日本の地方型芸術祭、特にリボーンアート・フェスティバルのような東北の場所をあえて「悪い場所」という表現をする美術評論家がいて。地震とか津波とか、昔からいろんな形で襲ってきていて。悪い場所って、不安定ということだけど。ユーラシア大陸の端っこから出てきて、太平洋プレートとかフィリピンプレートがせめぎ合ってできてきている。そうやってできた日本列島だから、山も多いし、海との距離も近いからこそ、特に食べるということに関して、命の多様な豊かさに恵まれているけれども、生きるというには結構大変な場所だったということ。
だから芸術作品というもののあり方で、ヨーロッパという安定した場所で、安定している場所だけど、血生臭い、略奪とか奪い合いの歴史の中で美術作品も受け継がれてきているんですというんです。それがその中で収まり切らず、大航海時代とか植民地主義に変わっていって、いまだに世界にいろんな歪みを残したままでいるという感じがするんだけど。
日本がもともと不安定な場所だからこそ、宮沢賢治のような自然観を通した利他みたいなものが生まれてきたのかな、とか思っていたんですけど。
岩井:宇宙規模で言うと、金とかプラチナって、ちょっとした超新星爆発とかブラックホールくらいではできないらしいんです。一説だと、ブラックホール同士が衝突した時くらいのエネルギーでやっとでき上がるみたいなことを、前にNHKの番組で観たことがあって。その説、変わっているかもしれないですけど。
いずれにしても、地球にあるありとあらゆる物質が、実は平穏なところからやってきたわけではなくて、人間なんか生きられないくらいとんでもない重力場と太陽エネルギーとか、いろんなところを経て流転して、今ここに自分たちを形づくっているという。奇跡のような偶然というか。本当に神秘的だし、すごく宗教的なものだと思います。一瞬のこの出来事、命があって、意識があって、心の有り様、自分たちで自我として自覚できるというか。星を眺めることができるという。
すべてがただの物理現象だとしたら、この意識というものが、なかなか説明がつかないんですけど。自我とか意識とか、自分を自分と感じているものというのが。生き物がなぜ生き物なのかと言うと、自然の物理現象で説明できない行動をしていくから生き物なわけで。それがたまたまこの星の上にあるという。
火星に行くと、昔は海があったそうですけど、もうないわけですよね。廃虚になってしまっているわけで。地球が一部砂漠になっている所はずっと砂漠なわけで。放っておけば最後、地球も恐らく火星のようになっちゃうんでしょうけど。そんな観測もありますから。月はどんどん地球から離れて、いつか遠い星になっちゃうらしいし、地球も最後は温度も上がってしまって、海もなくなって砂漠みたいになるみたいな。何かで見ましたけど。
宇宙の終わりとか、ドキュメンタリーとかを観ていると、不毛な気持ちも起こるんですけど、最後、宇宙がどう消えてなくなるか、みたいなものが、もうだいぶ分析されているとか。「こうやって終わります」みたいな。そうなんだ、という話ですけど。
そういう宇宙のダイナミックな動きの中で、つかの間、われわれが今、小さな星の上にとどまっているというのは、神秘以外の何ものでもないというか。人類は、人工衛星とかで月まで行って地球を外から眺めることができて、やっとそれを自覚できたので、せめてひとときは、その喜びをみんなで謳歌すべきなのに、いろんな無駄なこと、戦争とかいろんなことが続いているというところがありますね。
小林:いずれ人類は地球を出て。もちろん、今も計画ぼちぼちやりだしているけれど。地球以外の所で住んでいくという選択も含めて進化していくということではないかと思っているんです。
もちろん、すごく退行しているようにしか見えないようなこともあるんだけれど。でも、それでも少しずつ。よく言っているけど、「時間をお金に換えなさい」というか。「大人になるって、時間をお金に換えるということだよ」というような。宇宙時間的には本当にあっという間の時間の中で僕らはそういう風に生活してるんだけど。それも宇宙時間のスケールからしてみたら、もう少しでいろんなことが変わっていく可能性を持っていると思ったりするわけです。
今、僕らが言っている138億年前にできた宇宙というのも、その外はどうなっているのという話だし。
岩井:謎です。
小林:自分の意識をデジタル化して残しておくという話が、SFの世界では普通にあるでしょう。
岩井:ええ。
小林:岩井くんは、それができたらやってみたい人ですか。
岩井:いや、そこまではないですけど。でも作品は残りますから、それで十分な気はしています。個人的には、生命観というと、あらゆる生き物がそうですけど、一代で遺伝子がボロボロになって終わるはずのものを、遺伝子を残すという形で、ある種の永久機関をつくり上げているわけです。コピーは必ず、普通は劣化するわけですから、3、4代たてば使いものにならなくなるはずの遺伝子が、ちゃんと復元されて次につながっているという。この神秘が、物理的な輪廻転生を成し遂げているわけで。
最後死ぬ時は、そこに感謝しながら死んでいけたらなというか。「なぜ自分だけが死ななきゃいけないんだ」じゃなくて、あと残り70億人ぐらいいる仲間に感謝しながら、自分の命の灯を消せればな、みたいに思っているところがあるんです。死の恐怖たるやどのくらいか見当が付かないので、その場に立ってみないと分からないですけど。そういう思いは常日頃持っているかなと。
小林:ありがとうございました。良い話でした。ぼちぼち会ってご飯でも食べにいきましょう。もうちょっと寒くなったら、ジビエ系、マタギ系みたいなのもいいし。
岩井:ぜひ。コロナもちょっと収まってきましたね。また戻ってくる前にぜひ行っておきましょう。
小林:解放して調子に乗っていると増えてくるでしょうね。まだこの波が幾つか続くんだろうな。どうもありがとうございました。
岩井:ありがとうございました。
対談を終えて
久しぶりに岩井くんと対談をしましたが、読み返してみてお互いに歳を重ねたと、いい意味でですが思いつつ、少年性のようなものは変わらないな、と半ば達観して思ったりもします。
仮面ライダーに出てくるM&Aの話や、子供っぽい今の世界外交での言い合いや、グレたちゃんの登場など、子供の視点に近いものが良くも悪くもクロスしている時代なのかもしれません。
ある程度年齢が行った子供にもちゃんと伝えられるような発言や行動をしようよ、は僕の口癖ですが(まぁ多少のあやはありますが) それができるようにもなりつつあるけれど、同時にそれが単純化で済まされると言うことではダメなんだなという思いもあります。
ちょっと365日のマーチが鳴ったりします。まさか岩井監督との対談の後に、そのエンドロールで、っていうのもシュールですけど。
小林 武史
PROFILE岩井 俊二
1963年生まれ。1988年よりドラマやミュージックビデオ、CF等多方面の映像世界で活動を続け、その独特な映像は“岩井美学”と称され注目を浴びる。映画監督・小説家・音楽家など活動は多彩。監督作品は『打ち上げ花火、下から見るか? 横から見るか?』『Love Letter』『スワロウテイル』『四月物語』『リリイ・シュシュのすべて』『花とアリス』『ヴァンパイア』など多数。2012年、東日本大震災復興支援ソング『花は咲く』を作詞。2015年初の長編アニメーション『花とアリス殺人事件』、2016年『リップヴァンウィンクルの花嫁』公開。2017年6月『少年たちは花火を横から見たかった』(角川文庫)を上梓、同年8月には岩井俊二原作の同名アニメーション映画『打ち上げ花火、下から見るか? 横から見るか?』(総監督:新房昭之)が公開された。2018年10月に発表された小説『ラストレター』を原作にした初の中国映画『你好,之華(チィファの手紙)』が同年11月、中国全土で公開。 2020年1月に、同原作の映画『ラストレター』(出演:松たか子/広瀬すず/神木隆之介/福山雅治)を公開。同年7月全編ほぼリモートで撮影した『8日で死んだ怪獣の12日の物語』が公開、9月『チィファの手紙』が日本公開。