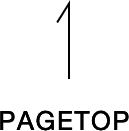vol.13 伊藤 亜紗 さん
小林武史が各界のゲストを招いてさまざまなテーマで語り合う対談連載。
今回のゲストは研究者の伊藤亜紗さん。
身体論や<利他>をテーマに掲げるプロジェクトなどで知られる伊藤さんと不安なこの社会をどう生きていくべきかを語ります。
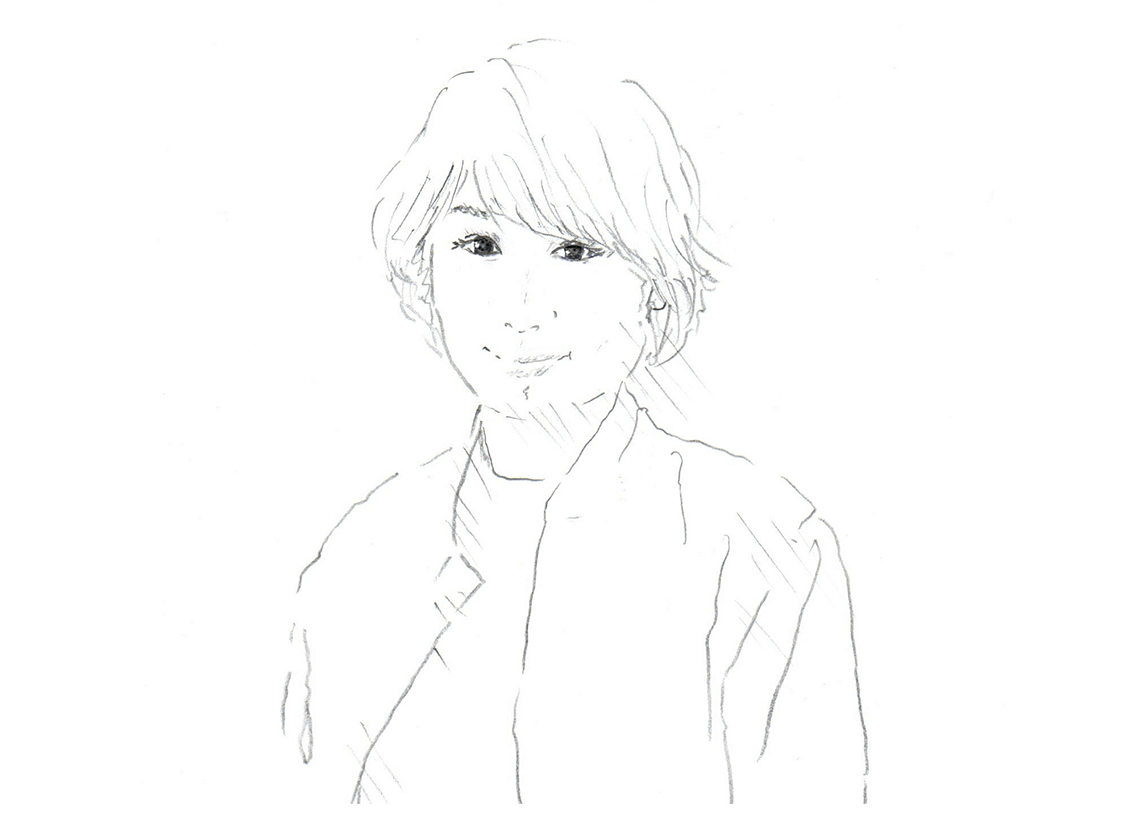
<利他>は「他者を信頼すること」から出発する。
小林:伊藤さんは肩書きとしては「美学者」になるんですか?
伊藤:はい。
小林:僕も言葉として「美意識」というのは使うんですけど「美学」というのはあまり馴染みがなくて。「美学」もしくは「美・学問」とでもいうのかな、はじめに伊藤さんが美学者として研究されていることを何かお聞かせ願えたらと思うのですが。
伊藤:はい。日本語で「美学」ってあまり言わないですよね。「男の美学」みたいな感じでそれだと違うニュアンスになってくるというか。
「美学」は学問的にはわりと哲学寄りのものなんです。哲学は「時間とは?」であるとか「存在とは?」のような概念を言葉で分析していくものですが、「美学」は感性とか身体とか芸術を言葉で分析していくもので。
これらはなかなかすぐには言葉にできないものばかりなんですが、がんばって分析していくともっと感じることが深まったり、うまく言葉にできた時には快感があって、そこが好きなんですよね。
小林:例えば美術であれば一方に違う表現として音楽というのがあるでしょう?そういう関係と、美学という「学問」を持ち出すということとはまた違うんですか。
伊藤:そうですね。美学が扱うテーマとしては芸術だけじゃなくて、例えば美学が始まった18世紀であれば「宮廷人の振る舞い方が優美であるかどうか」というようなことがテーマになりました。
当事は階級制が崩れてきていて、それまでは血統の良い人が立派という感じだったんですけど、18世紀くらいになってくると中産階級が増えてきて、血統は良くないんだけどお金持ちで社交界に登場する人が出てくる、いわゆるブルジョワというか。そうすると、人がどう行動すると立派に見えるかというような立ち居振るまいなどに対する関心が高くなったんですね。当時「宮廷人の振るまい」や「外交官の振るまい」といったことを指南する本が出版されたりもしたのですが、そういうものも美学研究の対象になります。
小林:それは「本質的に人が美しいと感じるということ」とどこか関わっている学問というものなんでしょうか。
伊藤:関わってはいます。典型的に言語化しにくいものとして「美」というのがあるんですが、英語にすると美は「Beauty」ですが美学は「Aesthetics」になるんですね。ただこの言葉自体にはあまり「美」という意味はなくて。これを日本語に翻訳するときに「美学」という言葉になっちゃったんです。そのなかで「美」は研究対象のひとつ、というところです。
時代や社会によって「こういうのがいいよね」というものは変わっていきます。文化によっても変わりますし。その、多様であり変化していく「こういうのがいい」というものを分析することが美学で、その研究対象のなかのひとつに「美」があるという感じですね。
小林:なるほど。じつは今日ここに伊藤さんをお招きしたのはあるシンクロを感じたからなんですが。
というのも、僕が音楽以外の活動としてap bankやKURKKUを始めてから20年近くが経って。直感的に始めた感じでしたけど、それの根幹にあるものって何だろうとずっと思っていて。いま思えばそれは<利他>ということじゃないかと。
仏教的な流れの言葉ですよね。普通に読めば「他を利する」というようなことなんだけど、漢字からさらに勝手に妄想というか、はみ出して、外から自分たちを見てみること。そういうことと、自分であるみたいなことの境目がくっきりあるものではないんじゃないか、みたいな感覚があって。
それで、この連載のタイトルもそうですし、僕らがずっとやってきている音楽フェスにもRitaという名前を付けようかなんて言っていたら、伊藤さんが<利他>に対してすごく発言されていると聞きまして。そういうシンクロが起こるんだなと勝手に思っていたんです。
伊藤:ありがとうございます。

小林:前にNHKの番組に福岡伸一さんたちと出られていて(2020年8月放送のNHK-BS1スペシャル『コロナ新時代への提言2』)「ナウシカ」のことに触れながら伊藤さんが<利他>について「ある意味コントロールしないこと」だとか、「待つことだ」ということをおっしゃっていて、共感できるなというところがありました。
伊藤:ありがとうございます。私も以前のこちらの記事で『風の谷のナウシカ』の話が出てきていて(vol.04 四井真治さん回)、「ああ、こちらでも」と思って拝見していました。
小林:それで伊藤さんはどういう思いから<利他>という言葉に行き当たられたんでしょうか。
伊藤:はい。私は研究者なんですけれども、研究者ってけっこう自分があまり得意じゃないことを研究したりするんですね。これまでの活動の中でも<利他>ということって、すごく面白いし重要なのはわかるんですけど、一方ですごく難しいなとも思っていて。
これはさきほどお話に出たBSの番組の中でも言ったんですけど、私は例えば障害を持っている人たちが「視覚がない状態でどういうふうに世界を見ているか」とか、「手足がない体とどう付き合うか」みたいなことを研究してきたんです。で、そういう方たちと関わっていると、”善意の塊のような人”がどんどん寄ってくるんです。寄ってくるというとなんだかヘンなかんじですけど、そういう人たちとの関わりが多くなるんです。
障害があると、周りの人と関わる機会が増えるのは当然ですが、そこに”善意の塊のような人”が関わってくるとちょっと怖いというか。というのも、そういう方の中では「私がこういう良いことをするんだから、障害を持っている人はそれによってハッピーなはずだ」という台本ができてしまっているんですね。障害を持っている人からするとそれに「付き合わされている感」になってしまうというか。その台本を実行する役者として障害者を演じさせられているような感じになってしまって、必ずしも本人のためになってなかったりするんです。
認知症の方と話していても、認知症があったりすると周りの人がすごく手を掛けてくれます。例えば、お弁当を食べましょうとなると、お弁当の蓋を取ってくれて、割り箸を割ってくれて、「はい、どうぞ」みたいな感じでやってくれる。でも、それは逆にストレスフルなことにもなるんです。本人からすれば時間がかってもゆっくり自分でお弁当を開けて、うまく割れなくても自分で割り箸を割って食べたいと思っていたとしても、善意で来られるから断ることもできなくて、それで挑戦もできなくなって自己肯定感がどんどんなくなっていく、といったようなことが起きる。
本当に「人のためって何だろう?」ということはすごく難しいですね。でもそこに私たちは間違いなく生きているし、そのことを考えたいなというのが<利他>の研究をスタートするきっかけでした。

小林:健常者が障害を持っている方々に「こうしたらいい」というシナリオを事前に持って接してしまうのは子どもと親の関係にも同じようなことがありますね。「あなた、これできないの?」とか、「あなたこれは得意じゃないんだから、ここだけはやっておかないと社会で通用しないわよ」とか。親は子を思って言うんでしょうけど、子どもはそうやってコントロールされてストレスを溜める。「世の中はこういうものだから」みたいなことで損得とか駆け引きみたいなことイコール生きることみたいに教え込まれてしまう。それは、子どもがつらい思いをしないで生きられるようにとか、食いっぱぐれないようにと親は思うからなんでしょうけど。
そうやってコントロールしようとする社会のムードというか、ルール化・常識化していくみたいなことは往々にしてあって。ただ、それはある種<利他>というところからいくと本質からは遠い話だし、セルフィッシュ(利己的)になっていきがちだなと感じます。
昨日もシェフたちと話していて、若い子はどうしても頭で考えた料理というものからなかなか離れられないということがありました。もっと食材のすばらしさに心が動いたときの喜びというのを素直に表せばいいのに、自分の調理の技術をひけらかす気持ちであるとか、どういうふうに相手に分析されるのかとかいうことにどうしても意識が行きがちで。
「自分の喜びが触媒みたいになって繋がっていく」というのは音楽からしてみれば当たり前すぎるくらい本筋の話なんだけど。どうしてそういうコントロールが生まれてしまうんでしょうね。
伊藤:そうですね、それはベースに「信頼」というのがあるかどうかなのかなと思います。<利他>は「他者を信頼すること」から出発する。自分が関わろうとする相手をまず信頼することが重要なのかなと。いまのシェフのお話でも、その食材を信頼していたらそれを自分の技術で制御して立派な料理にしようとか思わないだろうし。
私が最近興味を持っているのが「信頼」と「安心」の違いみたいなところです。今の世の中は「安心」を追求する方向に行っていますよね。教育なんかでもそうだと思うんですけど。
前にある学生と話していた時に聞いたのですが、その子は二十歳超えているんですけどGPSを付けられているというんです。ご両親からすると現在地が分かって安心なのでしょうが、本人からするとそれでは両親から信頼されていないと感じることになるでしょう。その学生はいつもコントロール下に置かれていることが当たり前になっていて、人から信頼されたり、人を信じるということが生まれてこない。
つまり「信頼」ということは、想定外のことや自分が思っていないようなことが起こることを肯定することじゃないかと思います。「安心」は「これをやったらこうなるよね」と思っていたことが「実際やったらそうだった」ということですが、でも「信頼」というのは「この人にやらせてみてどうなるか分からないけど、多分大丈夫だろう」と、想定外のことが起こることをわかったうえで任せることだと思うんです。
そうすれば、その想定外のことが自分の台本を超えていたとしても「それ、面白いね」と言って可能性をどんどん引き出せる。信頼関係の中で、計画通りではなくなっていくことを喜んで、それを力にしていくようなことが生まれるような世界です。<利他>ってそういうものじゃないかなと思います。
自然はもっと相互扶助的
人間だけが「競争」を強調してしまっている
小林:本当にそうだと思います。マルクス・ガブリエルさんが言うには「世界というものは存在しない。それぞれの人のイメージによって違ってくる」んだと。捉え方によって世界はそれぞれに違っていて、そこには、イメージの集積という言葉だったかどうか忘れましたけど、それらが重なり合っているだけだと。だからこそ確固たる「世界」というものに――僕はそう解釈しているんですけど――そんなにビビったりする必要もなくて、ただ描き直していけばいいというようなことなんだなと最近よく思うんです。
そう考えていかないと「世界はこういうものだ」「このほうがより合理的だ」「このほうが安全だ」というようなことがだんだん包囲網のようになっていってしまう。かつ、そういう意見をいくら聞いても相手は心を閉ざしていくでしょう。もし親が子どもに対して「あなた、もっと利己的に得な人生を生きなさいよ」みたいなことしか伝えられずに子どもが駄目になっていくとしたら、そんなのはディストピアというか、あまりにももったいないと思って。
僕は、もともと楽観的な男なのか、人間ってきっと乗り越えていくでしょう、いろいろなことも進化の過程のひとつでしょう、という思いがあって。ただ、未来を人のせいにばかりもしていられないし、自分に責任の一端はあるなと思っていて、音楽をやっている身でありながらもかれこれ20年ぐらいこんな活動をやっているんですが。
伊藤:もちろん安心も重要ですが、100%の安心なんてそもそも不可能だし、それを追い求める過程で信頼が失われてしまう。世の中が「安心」に偏ってしまう根本的なこととして、経済学における「競争原理」というのがあると思います。しかもそれは進化論の適者生存ような考え方と結びついていて、優れたものが勝つというのが自然の摂理であるように理解されている。
でも、それは本当の自然の姿なのか。いま私は東京工業大学という大学にいて理工系の研究者とかかわることが多いんですが、そこですごく思うのは、理工系の彼らが理解している自然というのは「競争原理」だけじゃないんです。もっと相互扶助的というか。太陽からやってくるエネルギーをどう循環させて、自分の老廃物をどう他者に渡して、それを他の生物の養分にして、そこで分解してもらったものをまた取り込むとか、そういうようなものです。それはべつに<利他>みたいなことを意識して考えているわけじゃなく、どうしようもなくすべてがつながっていて。もちろん自然界には競争という部分も入っていますがそれはあくまで一面的であって、相互扶助的な部分のほうがめちゃくちゃ大きいんですね。理工系の研究者はそこを研究しているので、自然を競争というイメージで捉えていないんです。
本来、自然とはそういうもので、おそらく利己的になっていては生きていけないんだと思います。人間だけが「競争」という面を自己暗示みたいに強調してしまって、あえてそういう動物になってきているところがあるんじゃないかと思っていて。ただ、自然から見たら相当人間は変というか(笑)。
小林:たしかによくある自然界で動物同士が食物連鎖の中で命を奪ってというような映像なんかを目にすると、それなりにショッキングに「生きるってこういうことなんだ」みたいな側面を見せつけられてしまうのかもしれないけど。
でも本当は、スーパーに行っても買いだめとかせずに今日の分の食材だけを買うみたいな慎ましい作業がベースであって、命を奪うことも含めて自然はそのなかでそれぞれが補完しあって必要な分だけで回ってますからね。
伊藤:そうですね。
小林:でも僕らはどうしても「競争」というところだけをクローズアップしがちで。まあたしかに、動物が昼寝ばかりしているとか、ただウロウロしているところだけを映像にしても面白くないというのもあるんでしょうけど(笑)。
伊藤:いまの社会では「競争」と、あとは「生産」にばかりフォーカスがいきがちですよね。生産的であるかとか生産量とか。自然界では生産量と同じだけ分解があって、そのふたつが同じ重要度を占めていないとサステナブルじゃないのですが。
小林:でも、そういう社会状況のなかでなにか伊藤さんとして「これはいい兆しだな」と感じるようなことはあったりしますか?
伊藤:いい兆しでいうと、最近<利他>のことでよく問い合わせを多くいただくんですが、それがいちばん多い業界はどこだと思いますか?
小林:どこだろう………。音楽業界じゃないな。
伊藤:それは小林さんからが初めてでした(笑)。でも遠くないですね。
小林:でしょう?<利他>の問い合わせでしょ、演劇とか映画とかそういうことでもない?
伊藤:ではないんですけどちょっと近い。正解はファッションです。
最近、ファッション業界の方から問い合わせいただくことが多くて。いまファッションの世界はかなり「分解」のことを考えてるみたいですね。服って作られた量の半分以上が廃棄されているらしいんです。それで国連貿易開発会議でも「世界第2位の環境汚染産業」とか言われてしまっていて。あとは労働の問題も。ファスト・ファッションがどんどん新しい服をモードチェンジして作ることで、発展途上国の工場の人たちにすごい負荷をかけている。それが搾取的な構造になっていて。斎藤(幸平)さんもそういうことを本に書かれていましたけども。
その環境と労働というふたつの側面でファッション界にはかなり危機感があるみたいなんですね。それで<利他>ということに注目をいただいてお問い合せいただくことが多いんです。こちらとしてはまったくそんなこと想定していなかったし、むしろいちばん利己的な自己表現みたいなイメージだったので。すごく遠いところから利他ということに注目されているというのがいい兆しというかすごく面白いことだなと思ってます。
小林:音楽とか演劇のような時間軸の中にいろんな思いを盛り込めるというものに対して、ファッションというのはある意味でシンプルな表現でファーストインプレッションを強く与えていくものだから。そこにある種のメッセージ性であるとか方向性を込める必要性というのはあるのかもしれないですね。そのうえで<利他>というのをこの時代のある種のカウンターとしての言葉と捉えたんじゃないんでしょうか。あくまで感覚としての話ですけど。
伊藤:たしかにそうですね。
小林:ファッションはもともとカウンターカルチャーと親和性が高い。Tシャツのデザインなんかはそのなかで価値や面白さが生き続けてきた文化だと思うので。そういうことを含めてファッションの人たちがこの時代に「利他」と言うというのは、考えてみれば合点がいくところはたくさんありますね。それはいい兆しのひとつではないですか。
ただ一方で、ファッションの人を悪く言うつもりはないけど、ファッションってちょっとしたブームが去るとまた次を見つけなくちゃいけないというところがあって。
伊藤:それはありますね。
小林:もうちょっとそれが表現とかいろんなところとつながっていくといいなと思いますけどね。
食の世界なんかでも、いまはカリスマシェフみたいな人が技術の粋を尽くしてそれにお客さんはただただ唸るのが礼儀みたいなことではなくなってきています。少なくとも世界のトップと言われているようなトレンドを引っ張っている人たちは「食材への感動」というかそういう表現になってきていて。
アメリカのバークレーに「シェ・パニーズ」というレストランがあって、僕がそのレストラン出身のシェフたちと仲が良いんですけど。その彼らにはいい言葉があって。それが「お皿の上に必要以上のエゴを盛らないようにする」というものです。人が食材と出会って響き合うということ、さっきも話に出ていたようにその感動とか喜びをそのままお皿に出せばそれでいいんだという。そういう意味なんだと思うんですが。
伊藤:たしかに料理ってある意味で人間技じゃないというか、究極的には人間が作ってないところがありますよね。それを思ったのは母乳について考えたときなんです。子どもが生まれると母親は子どもに母乳を与えますが、それは自分で意図しては作ってないわけです。今日は天気が悪くて雨が降るくらいの自然現象みたいな感じで母乳は出てくる。子どもはそれを100%信じて飲む。こうやって食って自分が介在しないところで回っていくんだなということにけっこう衝撃を受けました。母乳が料理かどうかはわかりませんけど、食の根源はそういうところにあるのかなと思って。
近道を通ってでも、どこを通ってでも、
何とかそこにたどり着く方法を見つけ出さないと。
気づいているだけではどうにもならないと思う。
小林:そうですね。ちなみに伊藤さんは食の面ではオーガニックじゃなきゃ駄目とか、そういうこだわりはありますか?
伊藤:私自身ですか?それほどこだわりはないんですが、でも<利他>を考えるうえで食は大きな手掛かりになるということは思っているので関心はすごくあるんです。
というのも、やっぱり人間の想像力には限界があるじゃないですか。さっき「外側から自分たちを見てみる」と仰られましたが、「地球規模」みたいな大きいことってどうしても考えが雑になるというか、細かく想像するのは難しい。いまのパンデミックもそうですけど、「世界的な感染の流行」とかいっても「あ、そうなんだ」と思うくらいしかなくて。自分の想像力で明確なイメージをつくり出していくのは難しいと思うんです。
でも食というのは、身近な毎日の活動で、かつ自然や環境のようなもっと大きいものと繋がってることだから。自分が食べているものがどこと繋がっているのかみたいなことを意識するだけでも、食を手掛かりにして自分の想像力を拡張できるのかなと思っていて。
小林:そうなんですよね。僕は食いしん坊だから食のことから繋がりのことを思ったり、循環のあり方に考えが派生していったりすることはけっこう多いんですけど。
それでいうと最近は、経済の合理性ばかりで何とかなるわけじゃないよねと思っている人たち、そうじゃないことに大事なことが潜んでいるよねと思うような人たち、そういうリベラルな人たちってデモや集会の現場だけじゃなく、オーガニックワインを出すようなお店にけっこう集まるんです。多様な命に対して敬意を払った料理、自然への謙虚さをもってできたワインを楽しむ場というのには、やっぱりそういう意識の人たちが集まってくる。
外食をする機会が何度かあるとしたらたまにそういうところに行ってみると、ひとりでSDGsを紐解かなくても環境でも人権でも格差でも、いろいろな問題についてわりと身近に話し合えるような場に出会えるという気がしています。
伊藤:なるほど。ちなみに日本のオーガニックワインって地域で言うとどのあたりに多いんですか?
小林:北海道とか山形とか兵庫にも新潟にも。すごく増えてきていますね。ワインに限らず、ウイスキーでもピュアな造り方をする醸造家が出てきてたり。
KURKKU FIELDSでも余計なエゴを盛らずに自然の力でおいしいものを作ろうということを常に考えていて、そこでは方向性として「生かされている」ということをよく言うんですね。以前の対談では英語に訳すちょうどいい言葉がないといわれてましたけど(vol.02 枝廣淳子さん回)、そういう感覚を大事にしていくと、「食べる」ということのなかに、自分は生きているけど他から生かされているということがいつも同時に起こっているというような感覚が自然と出てくる感じがありますね。
伊藤:面白いですね。家庭で作るときでも料理って「大さじ3杯」とか「180℃で何分」みたいにまず数字はあるんだけれど、そのこと自分の感性がせめぎあうというのがすごく面白いなと感じています。
レシピ通りするだけじゃなくて、その日の食材を感じるとか、自分の感覚を信じてそれと数字をうまく調整して、大さじ3と書いてあるけどちょっと疲れているから大さじ2.5にしようとか、今日の大根はサイズが大きいから4にしようとか。食材との出会いやそのときの感性的な部分を使うことで、料理という行為が生活のなかでとても大事な時間になっている気がしていて。
そういう意味で、このあいだ読んだ滝沢カレンさんの料理本がすごく面白かったんですよ。レシピに数字がいっさい出てこなくて、彼女流の風変わりな表現で書いてある。例えば唐揚げの下味でも普通なら「大さじ3杯の醤油」と書くようなところを「鶏肉全員に気づかれるくらいの醤油を入れる」とか。どれもとても食材に感情移入している表現なんですね。読む側としてはきっと彼女が想定したとおりにはきちんとできないんだろうけど、誰もが食材との対話をせざるを得ないような書き方で。料理ってそうやって、広い意味でのテクノロジーと感性のバランスみたいなものが問われるものだというのが面白いですね。
小林:そうですね。数字って目安として使えることはたくさんあるんだけれど。
音楽でも、きっちり割り切れる音楽と、ラテンの音楽などに多い割り切れない分母の何分の1の世界というのがある。本当はグルーヴとかノリとか揺らぎみたいなものって、その割り切れないものの間にあって。そこから思いもよらぬ気持ち良さが生まれてきたり、人を興奮させるスペクタクルのようなものが生まれてきたりするんだけど。
ただ最近の音楽だと、コンピュータに制御された正しさのほうがややもすると心地良く感じるというのはどこか安心感が先にきてしまっているからというところはあって。
例えば歌だったらピッチ(音程)も数字化できるわけです。441Hzが正しいAトーンだとか。それを感覚として合っているか合ってないかを判断するのって意外と簡単なことなんです。
レコーディングの現場でも「ちょっとずれてない?」みたいなことってよくあるんですけど、でも「ずれているが、どうした?」みたいなことなわけです。「ちょっとずれているのがそんな問題?」と言ってもいいくらいですけれども。そうやって過敏になってしまうのは、そうしないとどこか安心できないようなところがあるんだろうなと感じています。
最近よく話しますけれども、社会はかなり方向性をすごく見失っているんだと思っています。斎藤(幸平)さんが言うような、この資本主義経済が引っ張ってきた問題。それは多くの人がずっと前から感じていることだけど。
でも、みんな表面上は何事もないような笑顔で如才なく振るまっていないと「あなた、大丈夫?」と言われてしまう。暗黙のコントロールみたいな感じで。
最近お会いしてないけど宮台真司さんがこのあいだネット番組であっという間に加速主義者に変わっていて、「行くところまで行って一回完全に壊れたほうがいい」とあの人らしく言っていましたけど。
でも一方で伊藤さんは、じゃあどうするのかというと「待つ」と言う。どうでしょう、伊藤さんが仰る「待つ」というのはどうしたらいいんでしょう?
伊藤:どうしたらいいんですかね、難しい問題ですね。
さっきの、「みんなわかったフリをしている」というのは本当にそうで。私は美学の研究者で、大学では芸術の教員でもあるので、授業で学生に作品を作らせるんですね。で、その作品をそれぞれ自分で発表させるんですけど、いまの学生ってそのときの前口上がすごく長いんです。昔だったら作品を発表する前にそれを自分で説明するのって格好悪かったじゃないですか?でも彼らはすごく長々と説明する。
しかもそれが、自分の作品が同級生の感情を揺さぶったらマズいので前もって言っておきますが、というような感じなんです。「ちょっとこの映像、人によってはショックが大きいかもしれないので注意してください」とか「そういうのが得意じゃない人は僕の作品鑑賞しないほうがいいです」みたいなことを言ってから作品を流すみたいな。そういうのがすごく多くて。
とにかく彼らには他人の感情を動かしてしまうことに対する自己抑制みたいなものがすごくある。そこではとても狭い範囲でしか感じることが許されてなくて。本当は芸術とか音楽とかって自分が変わってしまうくらい揺さぶられてなんぼだと思うんですけど、それが起こらないようにすごく狭いところのレールをまず作って、この範囲内でなんとか収めようみたいな感じなんですね。それで、その制御を何もなかったかのように振るまうことをお互いにけん制し合っているみたいな感じがすごくします。見ていて怖いです。このままだと感情がなくなるんじゃないか?みたいな。
小林:たしかにそういう傾向はあるんだけど。それってどうしたらいいんだろう?
暗黙のコントロールでいうと、例えば片や「戦争がいつ起こってもおかしくない」とか、とんでもないひどいことが起きるという人がいるけど、そういう発言はあまり得にならないよと。逆にトランプなどがやたらとハッタリを言うけれど、それも実際そうはならないぞと。じゃあどこに行くかと言うと、とりあえずはみんな「経済の繁栄」というところで、そこからは誰も表面的には降りられない、というような。
伊藤:そうですね。
小林:このあいだマルクス・ガブリエルさんがNHKの番組で、このコロナの状況で、「メディアや社会や国が言っている危険なんてぜんぜん危険だと思えない。おまえらが心配と言ってもおれは全然大丈夫だ」というのが”1”だとして、「いやいや、ウイスルの全貌はまだぜんぜんわからないんだから僕は相変わらず引きこもっています」というのを”10”だとすると、いまはその間でみんながそれぞれにアクセルとブレーキみたいなものを考えながら生きていると。マルクス・ガブリエルさん自身は「僕は”7”ぐらいのところにいるのかな」みたいに言っていましたけど。
有機農業のことなんかでも同じようなことが言えて、有機かそうじゃないかみたいな二進法ではなく、それは割っていくいと何段階にもなるもっと立体的なものかもしれなくて。
僕はサステナビリティって進化の過程の問題なんだと思っているんです。その進化の過程のなかで、何段階もある考え方からなにをどう考えてどうしていくのか。そこには例えば斎藤幸平さんなら「脱成長コミュニズムでしかサステナビリティは起こらない」と”10”のことを言う。もちろん彼はをれを「あえて」だと言っているわけだけど。片や、自然界の殺戮みたいなところだけを抜き出して「弱肉強食・利潤追求・自由競争、以上」という”1”の考えがある。
この”1”から”10”のどの段階に行ったなら、それが社会に響いていって、ちょっとでも進んでいけるのか。そのためには、みんなが少しずつでも本質的なことであったり、人間の喜びを感じられるようになるべきだと思うっています。喜びというのは犬や馬にもあるかもしれないけれど、人間には人間にしかわかり得ない喜びというのがあると思う。もしそれを人間が知ったなら、人というのはもっと先に行けるものなんだと思っているんです。
僕はいずれ地球に寿命が来たとしても、地球と共に滅びるということすら超えていくべきじゃないかと思っている人間なんですね。だって宇宙の138億光年の歴史にしても当たっているかどうかもまだわからないし、その先がどうなるかなんてもっとわからないわけで。それでいいんだと思うんです。すべてを知ってしまうというなんていうことがたぶんあり得ないと思えるからこそ人は進化していくものなんだと思っていて。
どこに向かうかわからない、その先に何があるかわからないけれど、そういうことを想像するべきところまでもう人は来ている。でもそこで秘密主義みたいな構造とぶつかると、結果は<利己>がただ大暴発するディストピアで「はい、このゲーム終わりでした」というんじゃあ、あまりにもバカバカしいなという。
伊藤:究極の<利他>というのは、人間が次の種のために何かをすることかもしれないですよね。ただ、本当にすべては「わからない」んです。
いま世界がどんどんコントロールする方に向かっているというのは事実だと思うんですけど、とはいえ多分コントロールしきれないと思います。人間がわかり得る範囲よりも世界は広いし、複雑だし、変化しているので、絶対に追いつかない。すべてわかるって絶対にあり得ないことで。
小林:あり得ないですね。
伊藤:私はそれが救いかなと思っていて。
小林:本当にそう思います。とにかく、近道を通ってでも、どこを通ってでも、何とかそこにたどり着く方法を見つけ出さないと。気づいているだけではどうにもならないと思う。
その方法が脱成長コミュニズムということなのかどうかはまだわからないし、それもかつてマルクスがどう考えて、どう推移していったのかをひとつの手掛かりにしているというだけのことであって、絵に描いたように明確なこととして言っているわけではない。片や中国のような加速主義も半分入れながらの統制政治というのが永遠に続くとは思えないし。
伊藤:そうですね。さっきの「コントロールできない」でいうと、私ってけっこう影響されやすい性格で、去年の4月あたりに社会がコロナで緊張していると自分もすごく不安になってしまったんですね。そんなとき仲間のひとりで全盲の方が「ZOOM飲みとか流行ってるみたいだからやってみようよ」と声をかけてくれたんです。それから毎月1回くらいそんな会を開催しているんですが。
それであらためてわかったのが、障害を持っていたり病気だったりする彼らはこういうときは逆にめちゃくちゃ強いというか、すべてを制御できないなんていうことはとっくに理解しているのでこのコロナの状況下でもすごく冷静なんです。私が不安になっていても、みんな「そんなの普通だよ」といった感じで。
つまり「コントロールできない」ということって体がそれを教えてくれるんだなという感じがします。だから、いつも体と向き合っている人たちの言葉がすごく助けになったというか。それは、宇宙全体とか地球全体についての言葉ではなくて、すごく身近な体についての言葉ですけど、その力強さがすごかった。
人って思い通りにならないものを与えられているわけです。体というのは、こういう顔や体型でと自分で選択できるわけではなくて、偶然与えられたものを一生かけて引き受けていくというものです。そのなかには「こんなのどうしてくれるの」みたいなことだってある。神様の暴力というか。でも、じつはそこにはいっぱいヒントが含まれているというか。私はそこに手掛かりを求めたいなと思っています。
小林:でも、おっしゃる通りだと思います。実際、僕がやっているような音楽にしても、元は奴隷貿易とかとんでもなくひどいネガティブなことがなかったら生まれてないものです。生まれてないというか、今はまだなかったかもしれない。去年はコロナと並行してBLACK LIVES MATTERということも盛んに言われましたが、そうやって「ポジとネガ」、障害を持っている人たちをネガティブという言い方をするのもアレですが、そういうものってつながっている。そういうことは、僕が震災後に東北に行き、Reborn-Art Festivalという芸術祭をやってきたことの根幹にあったものでもあるんです。
そのなかで、やっぱり人にはそれぞれ役割があって。斎藤(幸平)さんとの話したときも「ホスピタリティという言葉とも近いかもね」ということを言っていたんだけど、人がそれぞれ他者の視点に立てるということ、そして響いていく、支え合っていくということをやっていかないと。
人それぞれのなかに通じていく、響いていくこと。ここがポイントなのかと。ポイントという言葉じゃないとしても、そういうものを見つけ出していくということなんだろうなと思っているんですけど。
そういうところで、伊藤さんの言葉は飾らないうえに懐にスッと入ってくるみたいなところがあって、テレビでお話しなさっているのを観て驚いていたんですよ。これからもぜひ良い役割を活かしていっていただきたいと思ってますので。
伊藤:ありがとうございます。
小林:またどこかでお目にかかれたら。今日はありがとうございました。
対談を終えて
伊藤さんには、僕は何か凄い力を感じるんです。
伊藤さんを中心にした今度出版される利他学の本もとても面白そうだし、
今後ap bankなどを通して活動していく部分にも、どうぞご指導ご鞭撻よろしくお願いいたしますという感じです。
昔、スピルバーグが監督した作品で日本名が「未知との遭遇」と言う映画があるのですが、
そこにデビルタワーと言う場所に人がだんだん集まっていくと言う不思議な力が描かれているのですが、
それに近いようなイメージというか妄想をしています。
(観てない人はごめんなさい)
先日は『利他学会議』をやってゲストに呼んでもらったんだけど、
そのアーカイブがしばらく見れるそうなので興味のある方はそちらもぜひ。
小林 武史
PROFILE伊藤 亜紗
東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター、リベラルアーツ研究教育院准教授。MIT客員研究員(2019)。専門は美学、現代アート。もともと生物学者を目指していたが、大学3年次より文転。2010年に東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻美学芸術学専門分野博士課程を単位取得のうえ退学。同年、博士号を取得(文学)。主な著作に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)、『手の倫理』(講談社)。WIRED Audi INNOVATION AWARD 2017、第13回(池田晶子記念)わたくし、つまりNobody賞(2020)受賞。第42回サントリー学芸賞受賞。