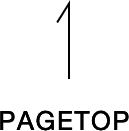vol.03 原川 慎一郎 さん
小林武史が各界のゲストを招いてさまざまなテーマで語り合う対談連載。今回のゲストはシェフの原川慎一郎さんです。
食の世界へ足を踏み入れるきっかけから、そこでの深いクリエイティブな想いを語っていただきました。
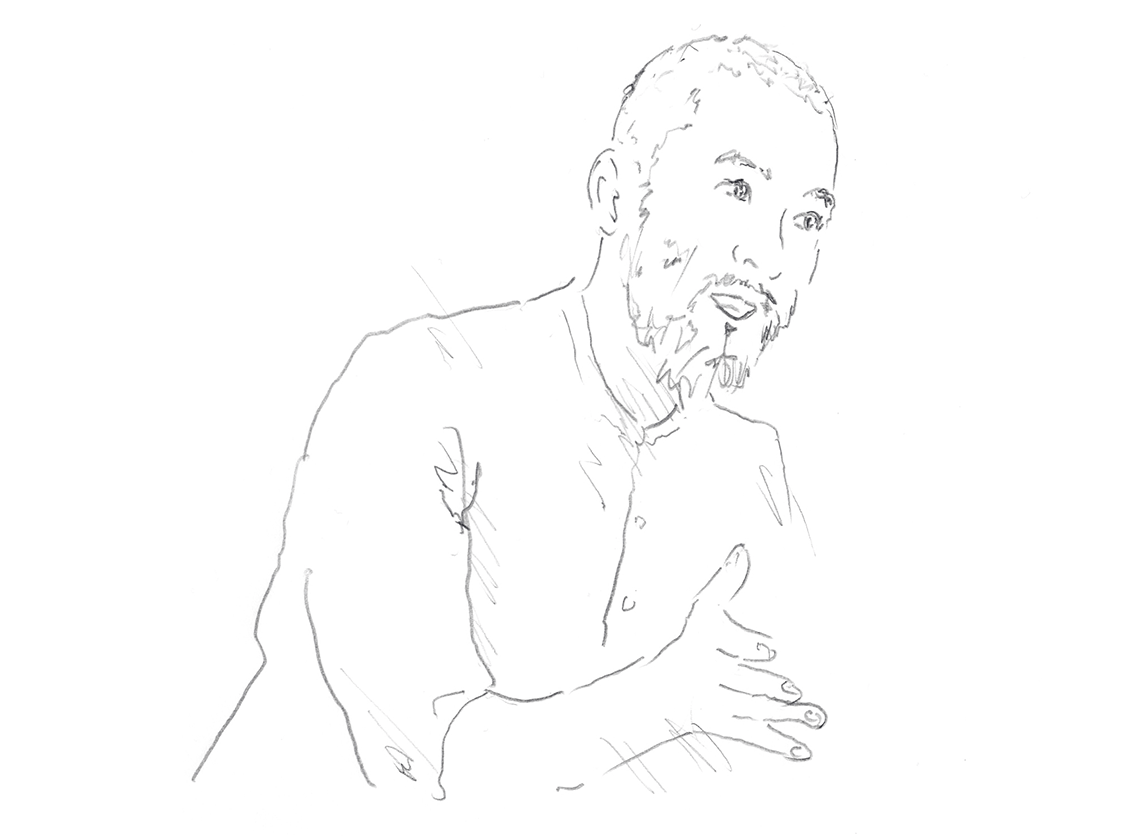
「なんとなく俯瞰で見た世界」への意識から始まった
小林:原川くんは、最初、報道関係にいたんでしたっけ。
原川:いえ。当事NHKの子会社の国際メディア・コーポレーションという所があって。そこはNHKの番組ないし海外の番組の放映権を取り扱う部署で、海外の番組を買い付けてきたり、NHKの番組を海外で放映するための権利処理みたいな。あとは映像の編集をしたりという部署にいました。
小林:じゃあ、世界で今どういうことが起こっているのかとか、そういうことに近い所にいたいとか、学びたいとかという思いがあったということ?
原川:すごくありました。中学生くらいの時から、日本に住んでいながら海外の、特にアメリカのニュースなどを観ていると、何となく俯瞰で見た世界を意識はしていました。日本だけでなく世界でどういう状態になっているか、みたいなことを。
小林:今、地球的、世界的サステナビリティということを大切にしていかないといけないと気づいている人がいて、原川くんはその一人だと思うんだけれど、まだ10代のころに、そういう世界と僕らが繋がっていたというのは、ニュースとかから入っていった感じですか?
原川:ニュース、映画。それこそ小林さんの関わった映画とか。
小林:「スワロウテイル」とか。
原川:ええ、日本だけに収まらない価値観があるようなものを通して感じていました。

小林:そこから食に向かっていくわけだけど、そのきっかけや理由を改めて聞きますが、どういうことだったんですか。
原川:僕は静岡の三島という田舎で育ったんですけれど、僕が幼稚園・小学校低学年くらい、30年ちょっと前くらいの静岡の片田舎は、普通の中流階級で祖父母は自営業だったんですけど、庭に畑があって、柿の木だったり、夏みかんだったり、果樹があって、トマトやナスやキュウリぐらいは育てていて。その庭で、生ごみは掘って埋めて、燃やすものは燃やして。ごみと言うと新聞紙か紙、牛乳の紙パックもまだなくて、空き瓶程度の暮らしだったんです。
祖母がその地域の主婦の集まりの中心の人間で、結構料理をしていて。僕も幼いながら、おうちに居ると「今日、お味噌汁作るから、鰹節これで削って」とか言われて削ったり。お豆腐屋さんが笛吹いて近所を回って。「お豆腐屋さんが来ているから、お豆腐買ってきて」と言われて買いに行ったり、という暮らしをしていたので、食は身近にありました。そういうベースがあったんだと思います。その原風景みたいなものを思い出して、ある程度大人になった時、社会とのギャップをすごく感じて。どこかで自分なりに縮めたいという思いがあったのかな。
成人して食を始めようと思ったのは、食べることは好きだったけど、別に料理がすごくしたかったわけではなくて。音楽も好きだったので、若いころはよくクラブに行ったりライブを見に行ったりしていたんですけれども。そうすると、そういう場はいろんな人が集まって、何か1つのものを中心に、カルチャーを共有して、その中で会話が生まれて、新しい発想が生まれていくという場が面白いなと思って。
でもだんだん夜更かしするのに疲れてきたので、レストランや居酒屋に行くようになったんです。そうしたら、そこにもそういう場があって、いろんな人たちが集って、食を囲んで会話が生まれて何かが生まれるという、その場が面白いなと思って。そういうことがやりたいなと思ったんです。じゃあ料理できたほうがいいなと思って、始めたんです。
お皿の上に自分のエゴを盛らないということ
小林:仕事しながら?
原川:仕事しながら。NHK関係で働きながら、当時は食べ歩いたり、クラブに行ったりはしていましたけれども。それをやめて、そこから料理の道に行こうということで、27歳の時に東京渋谷のビストロで働き始めました。
小林:渋谷のビストロ、何年ぐらいいたんですか。
原川:渋谷のコンコンブルという所に2年半くらいお世話になって、フランスに1年。その後に東京に帰ってきて、自由ケ丘のお店で1年。三軒茶屋のワインビストロで2年半ぐらいで、BEARDです。
小林:シェ・パニースには、夏のカリキュラムみたいな機会で行っていたんだっけ。
原川:シェ・パニースは、自分のお店を始めた年から。その前の年にジェローム注1と出会っているんですけれど、その年から毎夏、2週間とか3週間お店を閉めて、夏休みを取って行っています。
小林:BEARDをつくってから行くようになったの?
原川:そうです。
小林:知らなかったことばかりだ。フランスはどこだったんですか。
原川:ブルゴーニュのサンスという、かなり北のパリに近い小さな町でした。
小林:それはたまたまの縁があって、くらいのこと?
原川:いえ。最初、料理を始めようと思った時にフレンチにはまって興味を持ったので、フランス料理を勉強したいと思って、渋谷のレストランで働いたんですけど。やっぱり本場を見ないといけないなと思って、いろんな知り合いのツテで紹介していただいたレストラン、その当事二ツ星だったガストロノミーなレストランに1年お世話になりました。2008年でした。
小林:クラブなどで出来た幅広い人間関係あったでしょう。そこで本格的にフレンチというのを学びだすと、料理人としての世界の中にグッと狭く深く入っていくみたいな感じに変わっていかなかった? BEARDをつくるまでの10年近くの時間って、どんな感じで進行していったんですか?
原川:料理を始めようと思ってからはフランスの修業時代、自由ケ丘までの何年か、2009年ぐらいまでの期間は、それまでの人の繋がりはいったん断たれるような感じでした。経験がなかったので、ひたすら働いていました。
小林:料理の世界にどっぷり入ってきたんだね。
原川:そうですね。
小林:その辺がほんとに分からなくて。原川くんの料理って、フレンチの技法はこうなんだよ、みたいなことを主張するような感じがあまりしないから。あとシェ・パニース、僕も2回ほど行ったことがあるけれども、良い意味でベーシックだなと思うけれども、そんなに料理技術に特化した感じの印象はなくて。それはジェロームや原川くんにも通じるところがある。その辺りの修業時代みたいなものはどんなものだったのか、知らなかったのですが、そういう勉強はやってきたんですね。失礼しました。
原川:(笑)

(写真は『アリスのおいしい革命』(文芸春秋社))
小林:その上で、料理に何を求めているのか、求めてきたのか。今、シェ・パニースの出会いもあってかもしれないけど、料理に対しての型というか主義、原川イズムみたいなものがある感じがしているんだけど。食べるときにいつも信頼感を持って、毎回そうだよなと、その思いが正しいというか、その方向性への信頼がいつも料理の仕方などと合致する感じがあるんだけど。そういった料理法というか、哲学みたいなものって、言葉で語れるものはありますか。
原川:すぐに浮かんでくるのは、シェ・パニースだったり、ジェロームだったり、アリスさん注2が言う、「お皿の上に必要以上に自分のエゴや自分自身を盛らない」というところは、すごく共感して。その影響はすごく強いですね。
小林:あぁ、原川くんとジェロームってそういうことなんだよね。ちゃんとキャッチアップできてなかったけど、ものすごくいい言葉というか、分かりやすい言い方なのね。改めて聞くと。
僕も音楽をやる時、どこかでシャーマンというか、それを伝えていく巫女みたいなものというか、音楽がもともと持っている力というか動きがあって、そこを、たまたま何か浮かんだものをなぞっていくみたいな感覚。悪い意味でのなぞるというんじゃないけど。そういう仕事だなと思うところがあるんですけれども。そういう感覚にも、ある種近いものですよね。
原川:はい。その辺りは。僕が小林さんにすごく共感を持っているのはそういうところというか。自分もそうありたいと思っているんですけど。素直であるとか、正直であるとか、ぶっちゃけ、みたいな。ゴチャゴチャしたことはいいから、本当の真実は何なのとか、そういう核心的なところをちゃんと捉えて、それに疑問を投げかけたり、提示したり、表現したりということが好きです。それに対してシェ・パニースの考え方がすごくピンと来て。フレンチの、表現し過ぎたり加工・プロセスし過ぎたりというスタイルは、何となくピンと来なかった感じです、それはそれで一つのスタイルなんでしょうけど。
流動性のなかでの一期一会
小林:完成されたものとか、究極の技術みたいなものに行こうとしても、すごく危ういなといつも思っていて。うまくいっていることがずっと続くことも恐らくなくて。それも含めて循環していくということを受け入れる。
食材だって、いつも必ず、あそこの農家さんからいただいた食材が完璧だとか、完璧さを求めていくみたいなこと。そんな人はいないだろうけど。そういうことではなくて、それも含めた流動性の中で一期一会というか、今できることにちゃんと感性が反応していく、みたいなことが。それのほうが楽しいし、そのほうが豊かだという感じがするんです。そんなことですよね。
原川:おっしゃる通りだと思います。それはすごく思います。
小林:食を通じてのコミュニティというか、場のあり方とかつくり方とか含めて、より具体的な、この時間をどう回していくのかとか、そういうことに関してのセンスは、原川くんはすごくあると思うし経験してきていると思うんですけど。そういったことのためには何が大事ですか?
原川:それは音楽から、ライブだったりクラブだったりの世界からすごく学びます。あと、舞台だったり。そういう場は、人は感動することで心が震動して、それが周りの人たちと共感、共鳴し合ったとき、すごいエネルギーが高まると思うんですけど、音楽のライブは、そういうものが凝縮されていると思います。
背景は知らないですけど、1つのライブをされるに当たって、いろんな構成を考えられたり、照明だったり、ボリュームだったり、野外であればそのときの天気も左右するでしょうし。そういういろんな要素をコントロールというか、踏まえてライブがあって。そこにお客さんたちがどう反応するかで、化学反応みたいなものがバチッと起こったときに、ものすごく盛り上がる。ああいう経験がすごく、僕の今には役立っていて。
レストランも同じだなと。食も同じだなと思って。レストランという1つの括りで決まった2時間か3時間の中でも、1つのストーリーだったり、舞台だったり、ライブだったり、劇だと考えると、お客さんが入ってきた瞬間から数時間の、大げさに言うとショーが始まっているというか。その中で、照明だったり、音楽だったり、料理だったり、そのタイミングだったり、いろんな要素があって、それがお客さんとも共鳴すると、すごく豊かな時間になるというのは同じだなと思います。
そして、そういうことを人が経験すると記憶に残って、何かの原動力になったり、考えるきっかけになったりしていくのかな、ということを積み重ねて。
今の社会とか地球環境の中で、小林さんとかいろんな方たちが危惧している状況で、カテゴリーは関係ないんじゃないかなと。僕は食に携わっているので食という切り口、括りの中で、同じような志を持たれている方たちと、ジャンル関係なくコネクトしていくことで、広がりはどんどん大きくなっていくんじゃないかな。
小林:食べることは人間を含む生き物の基本で、絶対条件ですからね。食は繋ぎますよね。
そういえば今思いだしたこと。BEARDに最初に行った時、かけている音楽すごくいいなと思ったんです。原川くんがどこまで音楽に詳しいかとか、そういうことよりも、音楽がすごくいい役割をしていた。ブラインド・ドンキーよりも原川くん個人の感性がすごく感じられる場でもあったと思うけど。
僕らは言葉で、言葉だけがやり取りできる部分もあるけど、言語化してそれに頼って、それを取ったり捨てたりしていくことの中で、すごく強い力とかが関わってくることがあって、今よくある分断みたいなことが、図らずも起こっていると思う。それに対して、言葉にし切れない感性が、もちろん料理を通してだったり、音楽だったり、アートや舞台や、すべてだけれど、そういう表現や小さなその人イズムみたいなものが大事で。全部が全部1つで、何々派みたいに括られる必要はまったくないと思う。小さな分裂とかはむしろ必要で、そういうものも繰り広げながら連携していくみたいな。そういうことがすごく自然だし、大事だし。コロナの時代でも、経済リスクとコロナ感染リスクみたいなものの両天秤を、みんなバランス取ろうとしているんだけど、みんなそれぞれが、自分の自由と責任の下にバランスを取っていくというふうになってきている気もする。
それはむしろ楽しいことで。コントロールし切れると思っている人間がつくり込んだエゴみたいなものじゃなくて、不完全や不安定ということを許容した上で、分からないところを感性でなぞったり埋めていきながら、結局それが命の豊かさに繋がっていくということなんじゃないかな。
あと、フレンチを勉強してということもあると思うし、世界を見てきたところから振り返る視点からでも、日本の食の良さで、話してもらえること、ありますか?日本食という意味じゃなくても。
原川:食材という意味では、フランス料理から入っていったので、日本に帰ってきても、日本にない食材を探そうとしがちだったんです。でも経験を重ねる中で、そこにあるもので料理をしようと思うと、例えばフォアグラなんてないわけで。自然とフォアグラの料理はしなくなっていく中で、どんどん日本の食材と出会っていくと、四季がある感じと、しかも日本ってすごく長いので、北海道と九州、沖縄では全然シーズンが違ったりすることが、1つ面白いなと思います。
同じ食材でも、今ですとトマトとかズッキーニとかの夏の食材が、だんだん九州のほうから北上し始めて、東京界隈で採れ始めて、北海道でも少しずつ成り始めているけれども、九州のほうではほぼ終わっているみたいな。その状況を体験できるのは面白いなと。
山菜類だとかは、ほかの国でもありますけど、日本は結構盛んなものなんだなというのと。あと、魚のクオリティはすごいですし、処理や扱いは、ほかの国と比べものにならないくらいのレベルだなと思います。
レシピが先行しすぎているんじゃないかな、と思います
小林:醗酵って、良く腐らせると言うような、死の側と行ったり来たりということに関しての感性に、日本人は長けているなと思うんです。でも一方で、ふと思ったのは、最近イタリアンにしてもフレンチにしても、日本料理の技法なり、日本料理のある種の繊細さみたいなものが、すごく取り入れられているけど。その取り入れられ方がちょっとした形式的な感じになっていて、軽く感じることがあるという。何となく分かります?
原川:はい。
小林:フレンチとかイタリアンが持っている元々の、穀物にせよ、野菜にせよ、そういう力に対しての感覚は、欧米の人たちはすごく素直だなというか、素直にそういうことを大事にキープしているなと思うことはよくあります。
例えば、イタリアンのトマトをベースにしたソースでも、シンプルだけど深みがあるな、みたいな感じ。そういうことってありません?日本人は、ややもすると繊細ということにばかり行くかなと。ちょっと軽くなるというか。
原川:それは思います。何の影響なのか分からないですけど。個人的な意見ですけど、手を加えることというのはどういうことだろうというのは、よく思います。すごく細かく、繊細な仕立てにすることが手を加えるということなのか。トマトソースの、シンプルですけど、タマネギとか、ニンニク、トマトだけですけど、そこの見極めをすることなのかというところで。日本の料理は、そういうところよりも細かい部分に目が行きすぎているところがある気がします。
小林:ちょっとしますね。
原川:はい。
小林:日本において、技術というものの神格化でもないけれども、そういう技術と道、料理道みたいな何かが、食材が持っている命の野太さみたいなものから目が離れがち、と言うと生意気なことを言っているなと思いますけど、そういうところはあるのかもしれない。人によってだけど。
原川:人によってですけど。それは僕も感じていて。素材をパーツみたいに捉え過ぎている気がするんです。素材ありきというより。よくこの話をするんですけれど、現代の社会になったからすごく豊かになって、みんなが料理できるんですけど。最近、レシピが先行しすぎているんじゃないかなと、すごく思います。
この話、大体するんですけど、ラタトゥイユは、南のフランスで夏の時期に、トマトとナスとズッキーニとタマネギとパプリカとバジルが旬で採れたからできた料理だと思うんです。でも冬に、おいしい豚肉があるから、これの付け合わせにラタトゥイユ作るから、オランダからパプリカ買って、メキシコからズッキーニを仕入れてとか、流通だとかのおかげで、レシピありきで料理をできてしまうようになって、アイデアが先行し過ぎているんじゃないかなと。そこに旬のおいしい素材があるから、おいしいトマトソース作ろうよ、みたいなことにもう一度立ち帰ってみたらどうかなと思います。
小林:確かに、レシピというか。一方では、このあいだ森枝さん注3とも話したけれども、インドにはレシピ以前みたいなところもあるでしょう。カレーにレシピってもともと、イギリス人が初めて食べた時には料理名すらなかったという話とか。
カテゴリーとか、そういうことがそもそも。その認識とか、そういうことから始まっていくものではなくて、日々の中で命とちゃんと呼応していくということで十分な生き方みたいな。
根を生やして活動することの大切さと、
旅するような移動から生まれる新たな気づきや感動
小林:最後、これからのサステナビリティというか。10代のころ原川くんは、世界との繋がりとか、音楽やいろんなことの中で、どういうふうにして人間がここまで来て、どんなことに向かうのか、みたいな興味がすごく出ていて、今までの過程をざっくり、短い時間だけど聞いていても、伝わってくるものがあるんですけれども。旅の仕方みたいなことが。
でも一方で今、すごく地球の環境は、のっぴきならないところまで、もちろん食ということにもすごく影響してくるし。原川くんは九州地方とかでお店とかを考えているという話も聞いているけれど。素晴らしい食材の宝庫で、ものすごく豊かな場所だけれど、今までももちろん自然の猛威にもさらされてはいたけど、やっぱりすごい勢いで、特に大雨とか、極端な気象現象、気候危機になっていること。これからの原川くんの道筋で心配なことだよね。僕にとっても心配だし。僕らがクルックフィールズをやっている千葉だって、去年の台風15号とか、今年もまた台風シーズンがやって来るなという。身近に、どんどん加速的に悪くなっていると感じられるような環境の問題とか。原川くんとしては、どんなことに関わっていこうと思っています?
原川:すごく難しい問題ですけれど。いろんな立場で考えている自分が、正直いるんですけれど。単純に料理人と思ったら、気候変動によっていろんな地域が、今回も九州で大雨があったりという中で、自分だけのことを考えると、気候的にベターな地域に身を置けば、食材はそこにあるから、そこで料理すればいいやということも考えられますけれど。
例えば農家さんだったり漁師さんだったりは、その土地に、クルックフィールズもそうですけど、ここと決めて根ざした人たちは、そこで生きていくことを覚悟して生きていかれている。その覚悟を思うと、自分なりにそういう場に身を置く必要も、自分自身にとって必要じゃないかなと思うんですけれど。
その上で、サステナビリティのことに関しては、一人ひとりができることは限られているかもしれないですけれど、子どものころ、牛乳の空き瓶を返せば済んでいた幼稚園・小学校低学年から、小学校高学年くらいになってくると急にペットボトルが出てきて。瓶からペットボトルに替わっていって。ちょっと怖いくらいに、一気にペットボトルが自動販売機にワッと広がって。これって一生持つのかなと、子どもながらにすごく違和感と疑問を持っていて。案の定、今、マイクロプラスチック問題みたいなことになっているわけで。
でもこれも、あっという間に30年ぐらいの蓄積によってこうなってしまっているけれども、長いスパンで考えたら、30年でこうなってしまったら、大体それ以上の時間がかかるとは思うんですけれど、本当に意識をすれば、この先何十年かで変えられることは絶対あると思うので。一人ひとりができることで、日々忙しいから後回しにしてしまうことを、少しずつ、一人ひとりができることを、その人たちの立場でやっていくことしかない。
だから、今、九州の長崎に、すごく尊敬している岩崎政利さんという種取り農家さんがいらっしゃるんですけど。その方は40年近くその土地に根ざしてずっと種を取りながら伝統野菜、古来種のお野菜を育てていらっしゃる方ですけど。そういう人に触れながら土地に根ざすということを、擬似的にでも、もうちょっとコミットして体験してみながら、その経験を持ちつつ、引き続き旅を転々として、いろんな土地の人たちと、モノの大切さを伝えていけたら、自分なりにサステナビリティということに関して、何かできることがあるんじゃないかな。
それで食の場を介することで、自分のスタイルとして、ライブが好きなのでそういう場で、共感だったり共鳴があったら、一人でも多くの人たちがまた明日から、ちょっとプラスチックのこと考えてみようかなとか、ごみのこと考えてみようかなとか、自分が取る行動がどういう影響があるかなということに、ふと思いを馳せてもらえたりしたら、何か変わるかもしれないなということですか。
小林:でも、根を生やして活動することの大切さと、一方で、僕は「流動性」と言ってるんだけど、旅するように移動があって、そこでまた新たな気づきや感動みたいなものが生まれていくという。その二極を持っているという生き方は、全体と自分の個の自由みたいなことは繋がっているということを感じられる生き方かもしれないですね。
原川:それはすごく思います。最近よく頭に浮かぶ言葉で、「バランス」ってすごく大事だなと思います。小林さんがおっしゃる通り、今いろんな予期せぬことが起こる状況なので、絶対なんて、ずっとなんてないから、その状況にフレキシブルであれるスタンスを持っておく必要もあると思いますし。意識の持ち方とか、決め付けないとか、そういうことも大事かなと。
でも、これからもっと個人が自立することが必要じゃないかなと、すごく思います。その上で、社会だったり、全体だったり、その他とのバランス、共存を意識することも必要じゃないかなと。自分個人だけがいいというわけではなく、自分がしっかり立ちながら、周りとのバランスを取り合って全体を保つということも、すごく大事だなと、今のいろんな状況の中で思います。
小林:僕も思います。クルックフィーズも、あそこで働いている人は一人ひとり、自立するということを、独立するということではなく、自立するという何かを持っている人たち、目指している人たちが連携していくというようなことを目指しているんじゃないかと思います。連携がすべてだということでもなくて、そこのバランスであり、時には緊張感もあるような両極のあり方が、すごく大切なんだろうなという気がします。
原川:クルックフィールズの場は、それが場のスペースに詰まっていて体験できます。すごく面白い場ができたなと思うので。さらにもっと楽しくいい場所に、緊張感を持ちながらできていったら、訪れる人たちにとってのたくさんのインスピレーションになるんじゃないかなと思っています。
小林:ありがとうございます。
注1)ジェローム・ワーグ
オーガニックレストランの先駆けである「シェ・パニース」(注2参照)の総料理長を長年にわたって務める。度々日本にも訪れ、原川氏をはじめとするさまざまなシェフとのコラボレーションも行なう。2016年より日本に移住、原川氏と共に「the Blind Donkey」を立ち上げた。
注2)アリス・ウォータース
1971年、カリフォルニアのバークレーに地元のオーガニック食材だけを使ったレストラン「シェ・パニース」をオープン。スローフード運動の提唱や、学校の校庭を菜園にする「エディブルスクールヤード」など、子供の食育にも力を入れている。
注3)森枝 幹
シドニーの名店「Tetsuya’s」やミシュラン二つ星の日本料理店などで修行を積む。2014年、下北沢にレストラン「Salmon & Trout」を開業、シェフを務める。レモンサワー専門店のプロデュースや、水産資源の持続性を考える活動「シェフス・フォー・ザ・ブルー」に参加するなど幅広く活動を行なっている。
原川さんとの対談を終えて
ハンサムだし笑顔がはち切れんばかりでアクティブな感じもあるけれど、ちょっと異国情緒というか不思議な雰囲気を漂わせている原川くん。
2人で話したのは初めてなので少し緊張するかと思ったら本当になごやかな良い時間でした。BEARDを1人でやっていた原川君と、ジェロームとのブラインド・ドンキーの時代と、そしてまたスタンスを変えようとしている原川くんと関わり続け、食べ続けてこれて良かったと思います。これからもよろしくです。
小林 武史
PROFILE原川 慎一郎
「La Madeleine」(ブルゴーニュ、当時2ツ星)、「uguisu」(三軒茶屋)などのレストラン勤務を経て、2012年 目黒にレストラン「BEARD」をオープンし、話題となる。「Nomadic Kitchen」などの活動の傍ら、「Chez Panisse」での定期的なインターンシップを重ね、2017年、Chez Panisse元総料理長ジェローム・ワーグとともに神田に「the Blind Donkey」をオープン。現在、長崎雲仙市に新たな拠点を立ち上げるための準備を予定している。