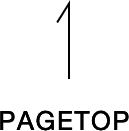vol.10 安田 菜津紀 さん
小林武史が各界のゲストを招いてさまざまなテーマで語り合う対談連載。
今回のゲストはフォトジャーナリストの安田菜津紀さん。
弱い立場にある人々に寄り添う活動を続ける安田さんに国内から世界まで幅広い話題で語っていただきました。
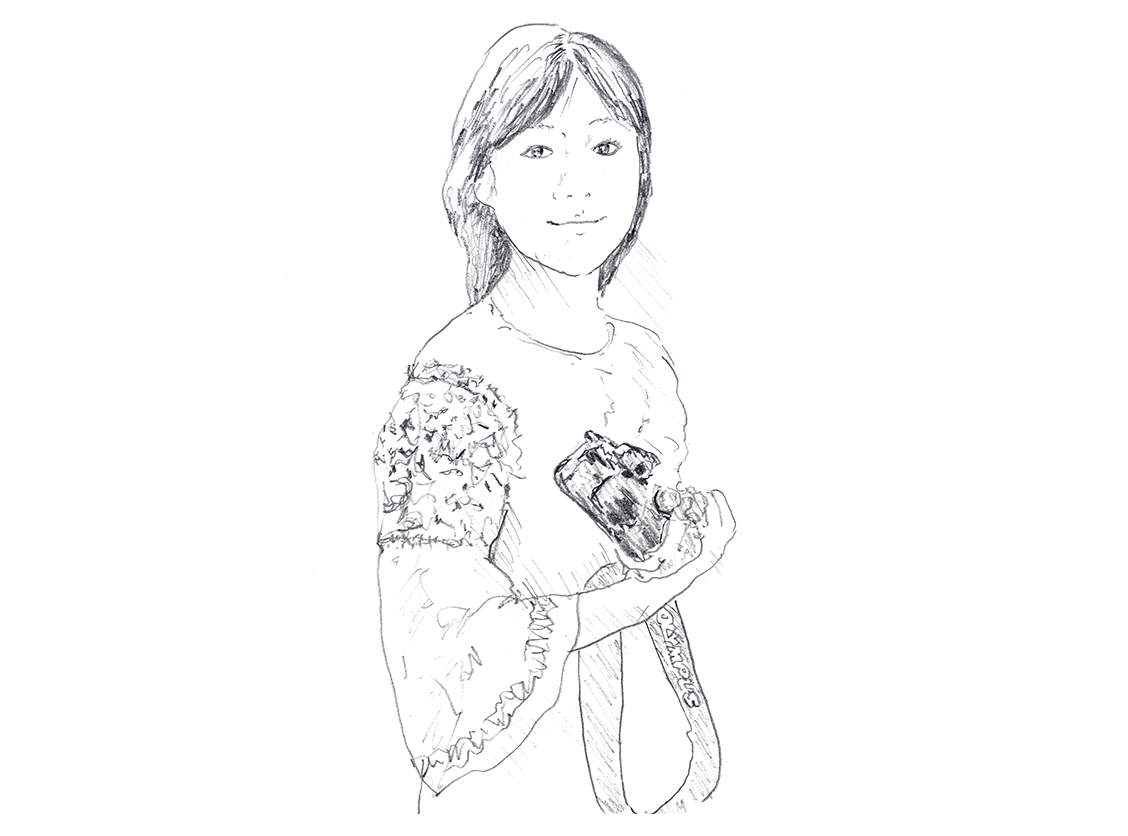
文化的に豊かなバックグラウンドを
持っている方を受け入れていくほうが
私たちの社会に豊かさを与えてくれるんじゃないか
安田:安田です。よろしくお願いします。
小林:ロック(69)の会で一度お会いしたことがあるんです。
安田:あと、YEN TOWN BANDのライブの後に、確かZepp Tokyoだったと思うんですけれども、少しご挨拶させていただいたことがありました。
小林:そうでしたっけ。ライブも3年ぐらい前ですね。
安田:多分、最初の接点になったのが「アイノネ」のジャケットに写真を使っていただいて、お世話になったのがきっかけのきっかけかなと。でも、「アイノネ」も2016年とかですよね。約20年ぶりの復活みたいな形でしたね。
小林:そうですね、4年ですね。2016年でしたね。忘れていた。
安田:私も久しぶりにその当時の記事とかを掘り起こして読ませてもらっていたところで。YEN TOWNの、国籍からはじかれ、国に守られない人たちの世界観と、その当時、シリア難民危機が大きく報じられていた時でもあって、岩井さんがお声掛けくださったご縁だったと思います。
小林:ほんとにそうでした。
安田:お世話になりました。
小林:こちらこそです。実は今、クルックフィールズという農場をやっておりまして。サステナブルな世の中をつくっていくことに貢献していく、というようなミッションを立てているんですけれども。2016年のころ、シリアの、難民申請はしてないんですけれども、サファットという男性が1年近く働いてくれていたんです。難民申請をして入ってきた人間ではないんだけれども、シリアにいられなくなって日本に入国してきた男性で、縁があって、ぜひ引き受けましょうということだったんですけど。
結局は離れることになりましたけど、彼と1回音楽でセッションしたことがあって。
安田:サファットさんと?
小林:そう。アフリカンパーカッションがあるんですけれども、それと、僕がピアノを弾いて、ちょっとテクノっぽいような音を流しながら一緒にセッションしたんですけど、すごいなっていう感じで。「好きで太鼓叩いていた」と言っていましたけど。血としてアフリカにも近いんだという。
安田:そうですね。シリアって、文化・芸術の交流点であり起点でもあるので。今日はしてないですけど、よくシリアの寄木細工のピアスとかをつけるんです。日本の寄木細工って、シルクロードを通ってシリアから伝わってきたものだというふうに言われているので、実はかなりその昔から交流があったところだと思うんです。
サファットさんがどうかは分からないですけど、国にいられなくなって、事実上の難民でも、日本はすごく門戸が狭いので、わざわざ難民申請をしないという方もいらっしゃいます。でも、もったいないですね、文化的に多様なバックグラウンドを持っている方を受け入れていくことのほうが、結果的に私たちの社会に「豊かさ」を何かしら与えてくれるんじゃないかと思います。
小林:ほんとにそう思います。アフリカの音って、奴隷貿易を経て北アメリカから僕らに伝わってくるというルートか直接アフリカみたいなこと感じだと思うけど、中東とかのルートでグラデーションのように伝わってきたりしたんじゃないかと彼との体験は思わせくれました。
安田:シリアの戦争なども、小林さんがずっと携わっていらっしゃる気候変動に密接ですね。
小林:そうですか。気候変動のことに関しても後で伺いたいと思っています。シリアの話も伺いたいこといっぱいあるんだけど。
コミュニケーションの厚みというか。
「これ、うちの子。これは隣んちの子で、おまえ誰?まあ、いいや」みたいな。
小林:最初に、そもそも安田さんってすごい人だなと思っていまして。そこにいる人たち、取り残されていってしまう人や心に対してアプローチなさっているんだろうなという感じがすごくしていて。なかなかできることではないなと。安田さんはどういういきさつでそういう道に入られたのか。フォトジャーナリストを含めて、ということになりますが。
安田:きっかけは、高校時代にNPO法人・国境なき子どもたちの活動に携わったことです。この団体が子ども記者を現地に取材派遣して、子どもの目線で子どもを取材する、「友情のレポーター」というプログラムをやっているんです。高校2年生の時に、レポーターとしてカンボジアに派遣してもらったというのがきっかけのきっかけですけれど、それまで特に国際協力や海外のことに興味があったわけではなくて。
私的な話ですけれども、私は中学2年生の時に父が亡くなって、中学3年生の時に兄が亡くなっていて、家族って何だろうとか、当たり前のように隣にいた人たちがいなくなってしまうという経験がすごく大きかったんです。まったく違う環境で生きている同世代の子たちが、家族とか人間関係をどういうふうに考えているのかということを、単純な興味として抱いて、最初は自分本位の気持ちで参加を決めたと思います。
カンボジアでは、例えば人身売買や、過酷な環境で生きている同世代に出会ったんですけれど、「自分はこんなつらい思いをして」とか、「自分はこんな悲しい経験をして」と言うよりは、「自分は今こうやって施設にいて保護されているし食べるものがあるけれど、自分以外の家族は何も食べるものがないかもしれない」とか、自分以外に守りたい誰かのことを語るという子たちだったんです。それが衝撃として、厳しい現状を見たのと同じくらい大きくて。
かたや、モノにあふれている日本から来た自分は、結局自分しか守るものがなかったんですね。「どうして友だちはもっと分かってくれないんだろう」とか、「家族は何でもっとやさしくしてくれないんだろう」とか。それは、一人の人間としてもろくなりますよね。いつか、彼ら・彼女たちみたいに、自分から誰かにやさしさを配るとか、自分から誰かを守れるような人間になりたいと、教えていただいたという感覚ですね。
何かをしなければいけないという義務感からスタートしたというよりは、いただいた言葉とか、教えてもらった経験とかに、自分はどういう形でお返しができるだろうか、みたいなことが原点の原点としてはあります。

小林:すごい経験を若い頃からなさっているように思うけど。この対談が「利他のセンス(A sense of Rita)」というタイトルなんです。でも、今の安田さんの経験とか話は、利他のセンスど真ん中だなと、正直思いますけれども。
安田さんが、最初にカンボジアに行ったのは何年?
安田:2003年の夏休みです。
小林:このあいだ、安田さんを紹介してくれた岩井監督と対談で。
安田:お元気でしたか?
小林:元気。引きこもって映画作っていたと。「ぼちぼちご飯食べに行っても大丈夫なじゃないかね。年内行こうね」なんて話をしていましたけど。YEN TOWN BANDの元になる『スワロウテイル』という映画をなぜ作ったのかというような、原点の話をしたんですけれども。もちろん、いろんないきさつは1990年代中頃にもあったんだけれども、彼がしてくれた話が面白くて。
その時の日本は病院みたいだって。保険もきいて、いろんなサービスがあるんだけど、文句ばかり言っている、病院みたいな感じがすると。いろいろやってくれるのが当たり前になるんだけれど、アラを探してみんなで病院に文句を言っている。
それに対して『スワロウテイル』では、海外からいろんな形で移民の人がやって来て、文句を言っていられる環境ではないんだけど、自分たちの中で、肉親や友人と何とか生きていこうとしているたくましさ、みたいなことを描きたかったと。
ざっくり言えば、そんなことを岩井くんが言ってたんです。
確かに、その当時の経済成長が成し遂げた後の日本って、一見クリーンで安定しているように思えるんだけど、人との関係を自分たちでどう築いていくか、みたいなもの。そういうところに力をかけなくなったというか。
安田:確かに。受動的というか、受け身というか。小林さんもいろいろ海外に行かれて感じられるところかもしれませんが、例えば、2003年に初めて高校生でカンボジアに行った時、コミュニケーションを能動的にしないと生きていけない環境だとすぐに気づきました。。
市場に行ったとしても、値札が付いてないから、「これ、いくら?」というところから始まって、「もうちょっと安くしてくれませんか」と、コミュニケーションが必ず、日常の何かをクリアするために生まれます。農村に行くと電気がないので、今日は私が薪を持ってくる係、私は火をつける係、ご飯の焚き加減を見る係、みたいな形になるわけです。
でも、日本に帰ってきて牛丼のチェーンなどに入ると、ピッと券売機で券を買って、スッとそれを出せば、身体的には生きていけちゃう。小林さんがおっしゃったみたいに、そんな便利な環境でも、牛丼屋さんで店員さんに些細なこと、理不尽なことで文句言っている人がいたりする。
自分から能動的にコミュニケーションを取っていかざるを得ないという状況ももちろんあるけれど、自分から能動的になることでの生命感を感じることができたカンボジアでの日々と、かたや、身体は生きているけれど常に受動的で、気づいたら自分からコミュニケーションに手を伸べる必要性が削がれていく日本、と考えると、確かに岩井さんがおっしゃった「病院みたいな」という言葉が重なりますね。
当時、『スワロウテイル』って、そういう見方を、小林さんもされたりしていましたか?すごく衝撃的な作品だったのは覚えているんですけれど。
小林:確かに、あの映画の向こう側にあったのが、甘やかされた病院のような風景というのは、俯瞰で見て分かる感じがしますね。
それに対して音楽的に言うと、90年代はもうデジタルの利便性が音楽制作にも使われていたんですが、特にYEN TOWN BANDの音は、わざわざ1960年代、70年代のアナログの機械を使ってレコーディングしたと言うことがあります。
YEN TOWN BANDはニューヨークでレコーディングしたんですけれども。その前にも海外には行っていて。野球で言うとメジャーリーガーみたいな。体力も技術もあるというような、ミュージシャンに置き換えても、そんなプレイヤーもいっぱいいるんだけど。
その時、ニューヨークで、その前に知り合ってた連中、アナログオタクですけど。アメリカにアナログのオタクのすごい連中がいるというのも驚きでしたけれども。あえて、うまいとかいうことよりも、slappyという言葉がありましたけど、うまいということに媚びない人間の味みたいなものが、いかにいいのかという、コミュニケーションの取り方でもあったんです。
アナログで、コンピュータとか一切使わないレコーディングで、今、コンピュータで出っ張りを全部整えたりできるんだけど、ムラというかそこに人間味がなくなっていくということがあるんです。本当にノーデジタルでレコーディングしていたんですが、管理していくということではなくて、人がその中で出会っていく時のデコボコも含めた良さを、ちゃんと記録していくというような感じでした。
安田:手触り感といいますか。いい意味でのザラッとした感じを、人間って求めていくんですかね。
小林:そうなんじゃないですか。ちょっと乱暴な言い方かもしれないけど。その感覚はまったく今の時代でも薄れてないんです。多分、これから50年たっても、そういう音楽に対してのアプローチはなくなることはないし。
安田さんが16歳の時にカンボジアに行って、そこで感じた手触りというか。「Reborn-Art Festival」2回目となる、2019年のコピーが「いのちのてざわり」という言葉なんですけど。「いのちのてざわり」みたいなことを、きっと感じられたんじゃないですか。それが、自分のことばかりで守りに入っている弱さみたいなものよりも、人とつながっていくことのたくましさというか。そこに生命力みたいなものを感じられたんじゃないですか。
安田:そうかもしれないですね。コミュニケーションの厚みといいますか、さっきの小林さんのアナログ感とか、人間味という言葉に集約されるのかもしれないですね。
例えば、初めて行ったカンボジアのスラム街で、小さい家の中に子どもさんがたくさんいたんですよね。お母さんに、「みんなお母さんのお子さんですか」と聞くと、「違う。これ、うちの子。これは隣んちの子で、おまえ誰?まあ、いいや」みたいに、緩やかにつながっていたんですよね、人同士が。例えば、町中でさも親しそうにしゃべっている二人組が、実は信号待ちでたまたま隣になった赤の他人みたいなこともあったりして。
日本に帰ってきて、東京の駅に降り立った時に、初めて強烈な違和感を抱いたんです。これだけ人間がたくさんいるのに、どうして目を合わさずに、こんなにあわただしく行き交っているんだろうとか。この駅、こんなにたくさん人がいるのに、どうして自分はこんなに寂しいと感じているんだろうとか。
その違和感を探っていこうとか、その違和感をそのまま形にしようとか、表現するということの、もしかすると原点になっていったのかなと思います。でも、多分、このままのコミュニケーションのあり方でいいのかなとか、このままの豊かさのモノサシでいいのかなというのは、9年前、東日本大震災で私たちの社会に大きく問われたはずなんです。
人間も自然の一部だけれど、
自然とは結局宇宙であるということ。
そういうものと東北はすごく相性がいい。
安田:私的な話ですが、私自身は、神奈川県の横須賀市の出身で、小泉家のお膝元です。米軍基地もある町ですね。夫の両親が岩手県の陸前高田市に暮らしていたので、そのご縁で陸前高田に通わせてもらっているんです。
小林さんがかかわっていらっしゃる石巻も、すごく命が近いといいますか、畑があって、海がそこにあって、“人間だけの町”ではないですよね。生きた、土とつながっている、水とつながっている感覚って、少なくとも私は東北に通って初めて実感できました。東京での違和感みたいなものに対する、もしかすると答えの一つがここにあるのかもしれないなと思ったのが東北だったんです。
すごく大きな聞き方になってしまいますけれど、東日本大震災が起きて、小林さんが改めて気づかれたことや、これが改めてこの社会に問われたな、ということって、すごくたくさんあったと思うんですけれど、特にこれまで東北に通われて感じられているのは、どういう点がありますか。
小林:よく言っていることですけれども、人間は自然の一部だということ、その上で、日本が必ずしも安定した場所ではない地震大国で、最近はさらに気候危機で、それは恐怖に近いものもあるけれど。だけど食の部分では、これだけ山があって、川がいろんなところに流れていて、海が近くてという。食だけではない、命の循環の豊かさ、四季がもたらす豊かさという、世界でも類い希な豊かな場所だとも思うけれども。そして東北もその一つだと思うんです。
震災後改めて、東北を意識して、出会うことになるんですけど。このあいだも岩井くんと対談している時、宮沢賢治の話が出て、農業や自然や宇宙の話になって、でも、まだ本当に僕らが知っていることは小さくて、たかが知れている。それに対しての思いというのは、恐らく昔から変わってない。僕はそれを「宇宙観」という言い方をよくするんですけれど。そういうものと東北というのは、すごく相性がいいなと思っていて。人間も自然の一部だけれど、自然とは結局宇宙であるということ。
それらと、僕らが理解することを超えてつながっているという思いとか、奇跡のような命に対しての感謝とか、そういうことが起こりやすい場所だし、震災の時にそういう思いが増大したんだと思う。それが僕は利他だと思うんです。
利他の思いというのが、あの時ボランティアとして集まった人たちもそうですけれども、僕の知り合いの漁師さんたちも、何のために自分が生きていたのかということが分かったと言う。「つながり」ということというか、「生かされている」という言葉も何度も聞きましたし。

安田:陸前高田の漁師さんたちは、「畏怖の念」みたいなことをよくおっしゃるんです。畏怖って、怖れでもあり、リスペクトみたいなものでもあるのかもしれないですね。
コロナなどにもいえることかもしれませんが、自然に対して人間が、経済という軸を元にして押さえつけるとか征服するということが、そもそも不可能なんだということを、本当は東日本大震災が突きつけたんじゃないかなと思うんです。
それこそ、先ほど小林さんがおっしゃったように、科学が、宮沢賢治の時代からいろいろ解明されているにしても、私たちはすべてを把握できているわけではないですよね。でも、町によって東日本大震災からの歩みはまちまちですけれど、陸前高田の場合は、12.5メートルの巨大な防潮堤をつくったりそれと同じくらい市街地を広大にかさ上げしたりと、かなり大がかりなんです。果たして人間に大地がつくれるんだろうかというところを、私も疑問、違和感を抱きながら見てきました。
結果、今何が起きているかと言うと、千億円以上の公費をかけ、かけてかさ上げもして大地を築いたはずが、半分が空き地という状態になってしまっていて、これまで求めていたものは何だったんだろうかということを、あの風景を見ながら感じるんです。
岩手県の中洞(なかほら)牧場って、ご存じですか。
小林:いえ、知らないです。
安田:山地(やまち)酪農を実践している牧場です。この辺は小林さんもお詳しいと思うんですけれども、近代酪農って、牛を管理して牛舎の中に閉じ込めがちで、牛の胃に合わないような穀物とかをどんどん与えてしまっているところもありましたよね。言ってみれば牛乳を作るマシーンみたいにしてしまう、アニマルウェルフェアにそぐわない形のものがあったと思います。
山地酪農は、切り立った山を、山羊みたいに牛が登っていくんです。人間がやることって限られていて。「どうぞ、どうぞ、山の中で自然に過ごしてください」と。糞尿の処理なんかも山任せなわけです。「子どもも自然につくってきてください。ただし朝と夕方だけ、すみませんが、搾乳のために牛舎に戻ってきていただけないでしょうか」ということで、牛が自由に山を闊歩しているような牧場なんです。
人間が命を機械化して食べ物を、ある種搾取みたいな形で取っていくのではなくて、そこに一定のリスペクトを持って、人間と自然が同じ空間を分かち合っていけるか、ということをコンセプトにしているところなんです。ご興味があれば、ぜひ訪ねてみて下さい。
小林:それはぜひ行ってみたいです。いつか僕がやっているクルックフィールズに一度遊びに来てください。
安田:お邪魔したいです。
僕はリターンを求めない投資家だから。
小林:お子さんはいらっしゃるんですか。
安田:いや、夫婦二人です。でも多分、牧場に行ったら子どものように遊ぶと思います。去年の台風の被害とか、大丈夫でしたか。
小林:それは大変だったんですけど。11日間の停電で。僕ら、太陽光を震災後いち早くつけて、みんな電力というところに売電していたんですけど。自家消費に対しての思いはあったんですが、それより先に台風が来てしまって。その後、オフグリッド、自分のところで電線に頼らずにエネルギー自給をするというやり方を研究していまして。来年1月、あと半年たたないうちに8割は自給できるようになります。
太陽光を主にしているから、今日みたいに曇りの日が何日も続くと、どうしても蓄電量が下がるんです。100パーセント、どんな日でも自給できるためには、ものすごい風呂敷を広げておかなくちゃいけなくて、それはエネルギー効率が決していいとは言えないということもあったりして、かなり研究しました。だけどまずは太陽光で8割の自給を目指すと言うことを進めています。
安田:ほんとですね。100パーセントではなくても、可能な限り自分たちで、というコンセプトが、実践できるようなフィールドで広がっていくと、電気に対する考え方とか価値観そのものが変わって行くような気がします。
お話の軸は違うかもしれないですけれど、原発が立地している福島県大熊町で、取材でお世話になっているお父様がいるんです。木村紀夫さんというお父様で、その当時小学校1年生の木村汐凪(ゆうな)ちゃんという娘さんと、奥様、お父様が、津波の被害で行方不明になってしまいました。お父様、奥様は見つかったんですけれど、娘さんがどうしても見つからなかったんです。
その後、靴の片方が見つかった現場があって、この瓦礫をどかしたら、もしかしたらいるんじゃないかという場所の目星はあったそうですけれども、原発事故があって捜索がかなわなくなってしまったんです。
その後、ご自宅が中間貯蔵施設の候補地になった時に、国側から説明会があって、「自分はまだ娘を捜索しているんですけれども」と木村さんが言った時に、国側の説明に来た方が、「すみません、行方不明者がいるって、把握していませんでした」と答えて、すごく愕然としたそうです。
探して、探して、よく諦めなかったと思うんですけれども、震災から6年がたつという直前に、マフラーとあごの骨らしきものが瓦礫の下から見つかりました。それまで線量の関係で、なかなか重機を入れることができなかったんですよね。上の娘さんに見せたら、「私、覚えているよ、このマフラー。あの時、お揃いでしていたマフラーだから」と。DNA鑑定を待って、ようやく汐凪(ゆうな)ちゃんだということが分かりました。
木村さんは、「確かに、原発事故さえなければ、娘を6年近く瓦礫の中に放置しなければならないような状況はなかったと思うし、怒りの気持ちが東電にはある。でも、あの事故を起こさせたのは自分でもある」ということを話していたんです。若い時は、原発立地自治体だから、「うちの町はこんなに整備されているんだぞ」と、ほかの町の人たちに自慢して歩いていたし、特にそこに対して疑問を投げかけたりすることもなく過ごしていた、と。
もちろん、福島第一原発の電気を、自分が直接消費していたわけではないけれど、でも、無批判に電気を消費し続けていたという意味では、広く見て自分も加担者だったと思うということを木村さんはおっしゃってました。木村さんの場合、自分の家のソーラーで、携帯電話さえ充電できたらいいかな、くらいの電力で生活しているんです。
もちろん、同じことがすべての人にできるわけではないですけれど、今の経済成長とかの話を聞いていると、豊かさの軸とか消費の軸を変えずに、小手先のことだけのことを変えているような議論が目立つような気がしていて。
小林さんが実践していることもそうだと思いますけれども、「今までの消費のあり方はこれでいいんだっけ?」とか、「そもそも豊かさの軸そのものが、もう限界に達しているんじゃないですか?」と、本当は根本から問わなければならなかったんじゃないかなと思います。
消費のあり方、豊かさのあり方の軸って、ご自身の中で価値観の転換点、ターニングポイントってありましたか?、。
小林:よく言うのは、ap bankをつくったのが2003年で。
安田:私がカンボジアに行った年、ap bankをすでにつくられていたんですね。
小林:2005年からap bank fesという、たくさんの人を集めるフェスをやるんです。その中で、環境問題の啓蒙活動になるような、ごみの分別とか、今こうやって安田さんと話しているようなトークイベントもいくつもやって。そのころから「脱成長」みたいな単語もすごく出てはいました。
ただ、本当に実感して、今の農業みたいな方向に行くのが、一番人に対して伝わる場づくりみたいなものが有効だなと思ったのは、経済にとっても大きな出来事である2008年のリーマンショックでした。
その時、ap bankのコンセプトで、クルックという事業が産声を上げていって。それは、東京でオーガニックレストランやオーガニックカフェをやる、みたいなことだったんです。その中でいろんなものをセレクトしていくわけです。フェアトレードのものであったり、リサイクルのものであったり。例えば牛でも、赤身の健康に育った岩手県の短角牛だったり、セレクトしていったんですが。
そこからもっと、太陽光のギフトから始まって、概ねこの地球は、そこから命ができている星だから、太陽光と微生物というものから生まれる、さまざまな命の循環を、自分たちでまずつくってみて、というのが今に至っているんです。
このあいだコロナで、経済も1回、どうなるんだ、みたいなことで止まって、お客さんもレストランとか行かなくなって、クルックフィールズの中にあるレストランも一時的に閉めることになりました。
僕も東京ですからしばらくは県またぎができない。東京もんは行くと嫌われる、みたいなことになって。1カ月以上行けなかったんですけれども。しばらくぶりに行くと、彼らはむちゃくちゃ元気で。命をつくっていて、それを自分たちで食べたり、場合によっては通信販売という形で人に分けることができる。
でも、すごくベーシックなことというのは、太陽光と土の力でどんどん食べるものを生んだりできるということ。傍らには牛とかがいて。牛はコロナのことは加減しないから、どんどんミルクもできていって、食べるものを作れているという。みんなそういった自然の力をすごく感じていました。
安田:伝わってきます。コロナ禍で、私も今、東京で暮らしているので、そもそも県境をまたげず、家からもほとんど出られないみたいな時に、小林さんのインタビューを読んで、「ずっとスタジオにこもりがちな生活をしていたからこそ、太陽の光のエネルギーとか力に気づかされた瞬間がある」と答えられていたのが印象に残りました。
私たちも、家にこもりながら、何とか少しでも太陽の光を浴びなければということで、ベランダで仕事できるような環境を整備してみたりしました。スーパーに行っても、求めているものがなかったりした時期だったじゃないですか。だから家のベランダに、ミントとか、ちょっとでも食べられる家庭菜園とかがあるだけで、すごく安心感みたいなものがあったりしました。こういう時に、クルックフィールズの方々のお話にも通じることかもしれませんが、、原点に気づかされるんだなと、実感しました。
これはコロナ禍に限らずかもしれませんが、私の周りの自分よりずっと若い方々、20代の子たちや学生さんたちを見ていると、今の社会のあり方の限界みたいなものが肌でよく分かっているな、と感じることがあります。生産性で自分たちを測られるのはいいかげん疲れた、という感覚かもしれません。例えば農業に興味を持ったり、東北に移住を考えたりという声を、私の周りでは結構聞くんです。
土にかかわることや、食にかかわることにずっと携わられていて、若い方々の意識の変化みたいなものって、感じられる時はありますか?
小林:あります。KURKKU FIELDSには50人くらいの人間が集まってきているんだけれど、ほとんどのみんなが、これから未来に向かって、経済を回していくためのシステムに組み込まれていくということに対して、すごく不安を感じていた人たちだと思うんです。もちろん、環境問題、サステナビリティという言葉も、小さいころから分かっていたと思いますけれども。でも、大学に行ったり、一回就職した人たちもいるけれども、それを辞めて集まってきているんです。
僕は場をつくっている。よく言うんですけど、「僕はリターンを求めない投資家だから」と。そもそも資本主義の理屈に外れたことを、やっているんですけど、一応カウンター的な気持ちで。
だけど、集まってきている人たちは、何か探すべきだと集まってきているんだと思います。探すべきだと思って、日々、これはこれで大変で、ある種の膠着状態みたいなものもそれなりに続くんだけど、でもやっぱり、またそこからちょっとみんなで集まって企んだりすると、ちょっとジャンプするんですけど。これが、周りの人が「あ、ジャンプしたね」なんて言って目に留まったりしながら、そうやって成長していくんだろうなと思うんですけど。
僕はもともと、自治していくということをやったほうがいいと思っていて。自分たちで、人間が集まって、誰かに「こうしたほうがいい」ということを学んだりするのはもちろん悪いことじゃないし、リーダー的な存在がいたり、外にもそういう人たちがいるのは、大切なこと、必要なことだと思うんですけど。その上で、自分たちでつくっていくというのが面白いと思うんです。
無垢なんだけど、外から見たらただの無知だということ
日本はその感じがありますね。
安田:自主的にどんどんやっていくコミュニティが生まれていく可能性って、すごくたくさん社会に秘められていると思います。
小林:ほんとにそう思います。応援していかなきゃ駄目だと思います。それらをどう連帯していくのかというのが鍵なんじゃないかという気がすごくしていて。全部が一つになることは難しいし。
クルックフィールズという場所も、ここに対しての忠誠心とともに一つになるとかということではなくて。そこには流動性みたいなものが絶えずあって、「ちょっと修業してきます」とか「旅してきます」みたいな人がいるのは全然アリだし。それをカバーし合いながら、僕らの体が10年前と今と細胞が全部違っているみたいに、連携をしながら進んでいくんじゃないかなと思っているんですけど。
安田:それって、一極集中の管理みたいなものとはすごく対極なものということですよね。
小林:と思います。それでもリーダーが大事だというのは分かるんだけれども、リーダーに依存していくということとは違うあり方が、生まれ得るんじゃないですか。この角度から見ると、この人はリーダーっぽく見えるとか、そういうのはあるし、それでいいんだけれど。実際は、少なくてもクルックフィールズなんて、僕が何もかもやっているなんてまったくないので。みんながいろいろやっていくことが本当に大切だと思っています。
僕からも質問させてください。今、コロナだと出掛けられないでしょう。フォトジャーナリストとして。
安田:はい。
小林:今後は少し、日本の中のものを見詰めていこう、みたいな感じになっています?
安田:そうですね。海外取材は1月にシリアに行ったのが最後です。こういうふうに対面取材というか、オンライン取材はしているんですけれど、さっきの“価値ある雑多さ”みたいなものが、オンラインだと、どうしても削がれてしまう。こんな暑い所にみんないるんだとか、匂いとか、五感の大半が削がれてしまうんですよね。そこに対する限界意識みたいなものはあります。
おっしゃる通り、国内では大熊に通わせていただいたり、コロナ禍であらわになってしまったものに目を向けています。例えば、飲食店で「Japanese Only」という札が堂々と出てきたりしていますよね。日本の中でもいろんな状況で、難民申請者も含めて在留資格のない人たちがいますけれど、公的支援からことごとく、そういう人たちが排除されてしまったりということがありました。日頃からあった格差とか差別の問題が、余計にあらわになってしまったところがあるなとは思っています。
今は、私の父が在日コリアンルーツだったということもあって、そのルーツを軸にしながら、ヘイトの問題ですとか、排斥の問題を取材していきたいと思っています。

小林:それもすごく大事なことで。でも間違いなく、Black Lives Matterも歴史的にも長い、根の深い。しかも近年もいろいろな、刑務所のシステムとか、どんどん入れてしまっていたという事実とか、いろんなことが明るみになって。
安田:『13th -憲法修正第13条-』というドキュメンタリー映画、ご覧になりましたか?
小林:まだ観てないです。
安田:すごくよくできていました。『When They See Us』と同じ監督で、今おっしゃったような刑務所システムが生々しく伝わっているので、機会があればぜひ。
小林:観てみます。そういうことが、コロナの中で浮き彫りにもなってきている。多様な存在、命の発露みたいなものがすごく見えるようになってきているから。ヘイトの問題もそうですけれども、ぜひ。僕らも頑張りますけど、安田さんには続けていってほしい。
安田:はい。この前の江守さんとの対談で、小林さんが最後に「尻切れトンボになっちゃった」と書いたところも伺ってみたいと思っていました。。
例えば昨日、『タイム』の「世界で最も影響力のある100人」に大坂なおみさんも選ばれましたね。彼女は、犠牲者である黒人の方の名前をマスクに刻んでいました。でも、日本ですごくバッシングが起こる。ヘイトの問題などは、モデルの水原希子さんもスピークアウトしていんですけど、彼女のもとにもおびただしい数の誹謗中傷が届く。
気候変動などは、欧米などを見ていると、すごくたくさんのアーティストの方々が当たり前のように意思表示をしていますよね。
小林:ジェーン・フォンダとか、ちゃんと、気候危機デモに参加して何回か逮捕されたりしていますよね。
安田:そうですね。どうして日本は、歌手の方や、アーティストとして影響力がある方々の声がなかなか聞こえてこないのか。気候変動や環境問題でも、発言している人は限られていると思います。Black Lives Matterなど差別問題になると、なおさら減ってくると思います。これは一体なぜなのかというところを、「別の機会があったらもっと話します」と書いてあったので、どういうところだろうなと。小林さんの目から見ていかがですか。
小林:でも、安田さんが、シリア難民とか、日本の受け入れ体制が万全ではないとか、阻害感を与えてしまうみたいなことというのと通じると思うんです。これはまだこのサイトで言ってなかったっけ。桃太郎主義という。
安田:ちょっと触れていましたね。
小林:桃太郎の母なのか、おばあちゃんなのかに、「鬼を征伐に行ってくるよ」みたいなことを勇ましく言う部分はイノセント、無垢なんだけど、外から見たらただの無知だということが、結構辛辣な桃太郎に対しての話ではあるんですけれども。割と日本はその感じがありますね。
周りも「頑張っておいで」と言うんだけれども、割と型にはまったことというか、一生懸命自分たちの周りを守っていればいいというようなことになりがちで。もう少し違う角度からものを見てみるという知恵というか、知性というところになかなか触れていかない感じがします。
これは同調圧力、あの時もいっぱい出たけど、ネットの世界でも問題になっていますが、変えていかないといけないのは間違いないと思う。けれどこの政局も、このあいだもまた、本当に自分たちが思ったことより、こうしておいたほうが安心なところというのか。安心したいんでしょうね。
安田:変化よりも、取りあえず現状維持のままで、みたいなことですか。
小林:現状維持で、肯定したいんでしょうね。あれだけ安倍政権の問題にいろんな方、不満を持っていたはずなのに、振り返って見た時に、外交で非常に活躍したと言っても、相手はあれだけ世界から「どうなのよ」と言われたトランプと、蜜月っぽく見えるというだけのようですけど。どうなんですかね。
トランプも、あんな乱暴なことを言いまくっているけれど、意外と、シリアのほうからもいったん撤退すると表明したり、本当の撤退ではないんでしょうけど。ただ、ビジネス的な損得みたいなところで、戦争を起こすことが基本的には不利益だというふうに思えばやめるという。
安田:そうですね。
緩い連帯をつくるには
間口が多彩にあったほうがいいんだろうな。
小林:僕は、軍需産業ということはあるんでしょうけど、その不利益ということがどこの国にも出てきているのではないかという気もするんですが。
もちろん、シリアのことも、僕なりにある程度関心を持って見ていますから。「アラブの春」の、ちょっと期待した解放していく力が、あんな形でシリア自由軍の人たちに武装されていってしまうと、そこからどんどんエスカレートしていくという流れは、一体誰が何のためにそういう武装を仕掛けていったのか。
安田:おっしゃる通り、トランプさんは、他国の状況というよりも、自国の自分のサポーターにいかに受けるか、みたいな感覚で動くところはありますね
経済効率で考えて、もう戦争は良くないねということ自体は、ある種望ましいことだとは思います。でもそれが、例えば強者に付く形で実践してしまっているところで、更なる混乱が生じていると思います。例えばイスラエル・パレスチナの問題なども、イスラエルとひたすら同調して、彼らの利益になることをやり、自国のサポーターが喜ぶことをします。エルサレムに大使館を移転したことも、その一つですね。その間、パレスチナ側は置き去りになります。
シリアからも将来的には撤退することが望ましいと思うんですけれど、去年のタイミングでいきなりアメリカが抜けたことによって、「力の空白」が生じてしまい、新たな火種につながってしまう、という事態になりました。アメリカが過激派勢力イスラム国との闘いで支援してきた少数民族クルド人の勢力が、その後、隣国トルコに攻められてしまうということがありました。現地の利益ではないところで動いているというのは、非常に悩ましいところです。
小林さんも「外交の成果なのか」ということをおっしゃいましたけれども、懸念しているのは日本の姿勢です。「僕たちはアメリカに100パーセント同調している」と一国の総理大臣が明言するというのは、かなり深刻な状況でした。どんなに蜜月であっても、どんな同盟関係であっても、「100パーセント一緒です」と言うのは、単なる思考停止じゃないですか。同盟関係であるのであれば、「トランプさん、そこは違うよ」と問題提起できてこその関係性なのかなと思うんです。それが廻り廻って中東にも不利益をもたらしてしまうというのは、すごく複雑な思いで見ていました。
小林:もう少しなんでしょうけど。ある種の公共性とか、今デジタルプラットフォームが偏ってしまって、ほとんど商品としての価値が。一般の人たちの情報があったりするわけですから。それがGAFAなどに全部占められているということが問題だという話はありますけれども。
最近、エシカルというか、倫理観みたいなものが。僕も、中学以来、倫理観なんて言葉使ったことないんですけれども。だけど、みんなどこかで気づいて活動しだしている。クルックフィールズの若者みたいにとか。いろんなところでそういう連帯が生まれようとしている中で、でも自明の理というか、今まであったことを変えない、それをヨシとするという動きに対して、それらを全部かみ砕くとしたら、いろんな多様なものも全部含めて、強者も弱者もつながっているという感覚。
それは今、SDGsなどで、SDGsだけですべてが解決されるとは思わないけれども、企業もいろんなことを、気候変動も含めて無視できないというところまでは来ている。無視できないことの中に、ある種の公共性を持った倫理観を育てていくということが大事なんじゃないかという気はするんです。難しいことだけど。でも、安田さんのように、僕も少しはそういうところがあると思いますが、大変なところに身を置くという。
でも、ネガとポジはつながっているということを、Reborn-Art Festivalでもずっと言っていたんですけど。むしろ、新しいポジティブの種はネガの中にあるというのは原理なんじゃないかと思うところもあるんです。
実際、僕が影響を受けてきた音楽とかは、奴隷制度がなかったら生まれてなかったのは間違いないことなので。だからもっと世界がいろいろ、混ざるところは混ざって、その中で命の手触りを。僕ら、奇跡のように命を授かっているんだけど、そのことをもっと喜び合えるような。そういう出会い方を取っていくようにするべきじゃないかと思います。
安田:公共性を持った倫理観を育てる、ということは今後も問われてきますね。小林さんが大事にしてこられた、気候変動に対する行動とか、問題意識とかも、世界に広く訴えかけてきたグレタさんを叩いたり冷笑したりという動きがネットでは目立ちました。さっきの小林さんの話で言うと、彼女は別にカッチリとしたリーダーということではなくて、たまたま彼女が始めた行動が、いろんな所で連鎖していった、ということだと思うんです。日本でもバッシングするような声があって、すごくもったいないというか。
冷笑で世界は良くならないじゃないですか。でも、その冷笑をものともせずに行動している人たちがいますよね。今日の夜も、江守さんとグレタさんが始めた行動に連帯している若者たちとLIVE配信でご一緒することになっています。東京はこういうやり方をするけど、岩手は岩手のやり方、みたいな形で多様に行動している。すごくそこに希望の種がある気がしています。
でもそれって、小林さんが大事にされているところと同じで、その組織をガチガチに統制するというところでは絶対に生まれない動きではないかと思います。緩く連帯していって、それこそ生き物のように人が出たり入ったり、そこの中で成長したり、また帰ってきたり、という柔軟性があるからこそ継続できるものなのかもしれません。
大切なのは、細かな違いはあるけれど、でもここは連帯できるよね、というポイントを見つけるというところだと思います。
小林さんが、別のインタビューで答えていらっしゃいましたけれども、「牛と戯れに来なよ」とか、楽しいフック、ワクワクするきっかけがあってもいいんだと思います。音楽もそういうですし、緩い連帯をつくるには、間口が多彩にあったほうがいいんだろうなと。
小林:そんな気がします。とにかく時間をお金に換えるというような社会だから。そこからじゃなくて何が生まれるか、今日何をしにどこに行くかというだけじゃない、さまよってみて出会えることを、勘を持ってそこに向かうみたいな。そういうことが大事なんじゃないかという気がしていますけれども。
安田:実は気になりつつ、Reborn-Art Festivalにお邪魔できたことがなくて。
小林:来年、震災から10年の3.11の時に、人をあまり集められないから、電波を使って何かするというアイデアがあるんですけれども。でも、そこに何かアート作品があって、その作品の置き方を考えたいなと思っていて。それを見た人が行ってみたいと思えるような仕掛けをまずつくろうかと思ったりしています。
来年は、利他が出てくるんです。流動性ということもそうですけど。流動性って、津波ももちろんそうでしたけど。でもあの後に、聞いたことないですか。養殖とかをやっていた人たちが、全部根こそぎ、そこにたまっていたヘドロみたいなものも持っていかれて。
安田:よく聞きますね。
小林:でも、もう1回養殖をやり直す時に、そういう状態をつくらないような、サステナビリティにつながる漁業、養殖を始めた人がいて。
昔からとんでもないナイル川の大洪水が肥沃な土地をもたらしていたと。ピラミッドの所も、昔は砂漠じゃなかったと言いますもんね。いろんな自然の猛威が、それこそとんでもないネガティブが新しい出会いをつくってくるというのは本当だと思うので。
安田さんも恐らく、小さいころからそういうことをバネにする面白さを知っていた。
安田:そうですね。陸前高田も結構しょっちゅう行かれたりとかは?
小林:僕も何回か行きました。3、4回は行っています。
安田:話が若干戻りますが、陸前高田の漁師さんたちが「最近、伊勢海老が時々網に掛かる」と言っていました。もっと南方でしか獲れなかったとか。ウニが最近は、全然獲れなかったり、獲れても中身が詰まっていなかったりするみたいですね。「水温が下がらないと餌になる昆布が抱卵しなくて、昆布が育たないとウニが駄目だから」と漁師さんたちがおっしゃっていました。漁師さんたちは水温を日々見たり、敏感じゃないですか。そこで一つの海藻が駄目になると、当たり前ですけど、ほかの生き物もそうなんだと、ちょっと心配ですね。
石巻にも多分、いろんな影響が出ていると思いますけど。
小林:来年、Reborn-Art Festival、もしかしたら秋とかの開催です。それでさらに22年の春とかに、2期に分けるみたいな構想もあったりするので。ぜひ。
安田:行きたいです。
小林:クルックフィールズのほうもHARVESTの時に、このあいだトークもやったんですけど。安田さんも1回ぜひ話してもらったほうがいい。ぜひお招きさせていただきたいです。
安田:恐れ入ります。ありがとうございます。その前に牛ちゃんたちに会いに行きます。
小林:安田さんの明るい生命力に、いっぱい反応がありますよ。
安田:ありがとうございます。多分、お邪魔したたら、自然の中でさらなるエネルギーをいただけると思うので、ぜひ。
小林:ありがとうございました。
対談を終えて
特別な存在の方なのだと思いますが、あえていうなら特別に愛が深いとか優しいとかではなく、普通に素敵な方なのだと思いました。
何が言いたいかというと、彼女のように特別な何かを持っているから周りのことや未来のことを思ったりできるのではなく、みんなの中にあるものと普通につながっているのだと思います。
アメリカ大統領選挙の最中ですが、やりとりやパフォーマンスがどんどん極端になっているのを感じます。
何が言いたいかというと、どう反応するかだけじゃなく、どう考えるか、思考停止になるのが一番怖いということです。
というわけで、安田さんとはまたゆっくりお話をしてみたいです。
小林 武史
PROFILE安田 菜津紀
1987年神奈川県生まれ。NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)所属フォトジャーナリスト。同団体の副代表。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『写真で伝える仕事 -世界の子どもたちと向き合って-』(日本写真企画)、他。上智大学卒。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。