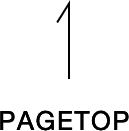vol.14 皆川 明 さん
小林武史が各界のゲストを招いてさまざまなテーマで語り合う対談連載。
今回のゲストはminä perhonenデザイナー・皆川明さん。
その作品からも伝わってくる豊かな世界観と、それを支える深い洞察をじっくりと語っていただきました。
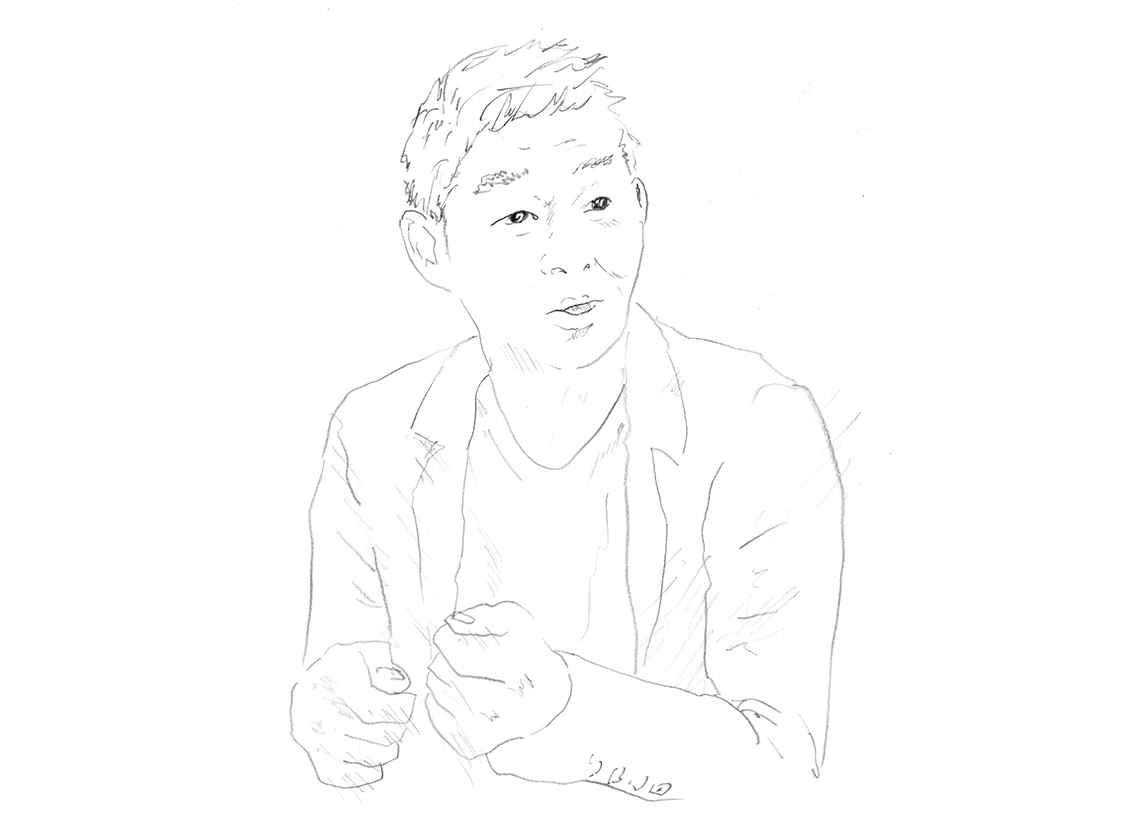
「奪い合うシェア」と「分け合うシェア」。
小林:皆川さんにはReborn-Art Festival(以下RAF)の第1回目の時にご参加いただいて。
皆川:そうでしたね。Tシャツのデザインを。
小林:あれは大人気の物販になったんですよ。その節はありがとうございました。
で、そのRAFも、これはまだちょっとコロナの状況をシミュレーションしているところですが今年の開催を予定していて、そのテーマが「利他と流動性」なんです。
この対談連載のタイトルにも「Rita」とつけているのですが、この「利他」という言葉は、特に漢字の印象もあってか、そのままだと人は慈善事業的であったり福祉的なことを浮かべがちなんだと思います。でも、僕が思っているのは必ずしもそういうことでもなくて。もっと他を利するということの大切さ、そういうものに共振したり共鳴したりすることが大事じゃないかと思っているんですね。そう言う意味で、皆川さんの作品やいろんなところにもそういったものを感じています。
皆川:「利他」ということでいうと、人ってなにか限られた資源があるとそれを早い者勝ちでより多く取っていこうとする人間心理があるようなんだけど、一方でそれが限られているならば分け合おうじゃないかという心理も生まれたり、なかなか面白いなと思います。
産業革命からの「どんどん作れば豊かになる」というところから、現在では「このままだと地球に限界が」となって、今度は「じゃあどのくらいの量が正しいんだろうか?」という知恵がいろんなところで働き始めていますよね。
僕らは普段「シェア」という言葉を2つの意味で使っています。ひとつは企業などが言うマーケットの専有率として使う「シェア」。でも、人が物や感覚などを分け合うことも「シェア」と言う。これはずいぶんと意味が違いますよね。
経済やビジネスの範疇で語られる「奪い合うシェア」では、結果として「シェアを得た豊かな人」と「シェアを奪われた豊かでない人」の二極が当然出てきてしまいます。
でも「分け合うシェア」では、渡す側と受け取る側の双方に幸福感が増す。その際、渡す側は自分の喜びを減らして相手に与えているわけではなく、逆に喜びは減らないどころか新たに生まれてもきます。このことは、物質と違って幸福感というものは無限にあるものだということに気付きやすいかなと思いますね。この視点ですべての物事を考えていくと、物質も感情も、人間の関係性が変わるんじゃないかという気がしているんですけど。
小林:本当ですね。自分が共鳴するよう中で出てくる喜びは減らない。これだけ与えたら自分はスカスカになったよってものじゃないですもんね。
そういう喜びの豊かさにみんなが入っていけるような循環を創る必要があるんだろうと思うんです。そういうことに誘(いざな)っていくというか。
皆川:あと「奪い合うシェア」ではどうしても全体のスピードが速くなりますね。「早く取らなきゃ」「早く作らなきゃ」「早く売らなきゃ」というふうになってくる。だけど「分け合うシェア」はけっこういいバランスで時間軸が適正になりやすいんです。必要な分だけでいいので、余剰だとか無駄になってしまうようなものを焦って作ったりせずに、全体の時間が少しゆっくりになっていく。
どういうことかというと、良いものは少し時間をかけて作って、時間がかかった分の値段にする。そしてそれは良いものだから、今まで雑に作られたものよりも長く使えるし、人が長く使いたいと思うからこそ世の中に長く残る。そうすれば価格の高い分も使っている時間が長くなれば結局はバランスが取れる。そして必要かつ少ない量のモノが暮らしの中に長く留まることになります。10倍の値段でも10倍の期間使えば支出額は変わらない。経済的にも矛盾がなくなると思います。
これなら生産者もじっくりととにかく良いものを作ればその価値に見合った値段で売ることができます。これまでのように、安く早くたくさん作ってそれが早く消費されていってしまうものと、結局はどちらも変わらないという。
経済全体としての総量は変わらないすれば、どっちが幸せかという観点で「分け合うシェア」の少しゆっくりと動いていくサイクルにしていったほうが良いんだろうということですね。僕らはそう考えて、なるべく長く着られる服を作ろうとしています。そのためにも生産者にじっくりといい職人仕事をしてもらうというふうにしています。
小林:そういう作る喜びと経済のあり方がちゃんと手を結んでいるということって、皆川さんの作られる作品や洋服が好きな人はしっかり感じていらっしゃるんだと思います。そこに信頼が生まれるし、変な話、皆川さんたちが暴利をむさぼっているなんていう感じもまったくしないだろうし。
「利他」というだけではなく執着しない「流動性」を
小林:ただ、世界的に現在の社会では「これだけの安さのものがこれだけの品質でできています」とか、そういった価格のインパクトで人の関心を奪う、誘うというよりもうちょっと強烈に引っ張りこむというようなことがずっと続いてきていますよね。
皆川:そうですね。品質と価格というところで言うと、その品質に対して「安い」と感じたときにはどこかバランスが崩れているかもしれないです。それは例えば生産される際の労働環境が非常に悪い可能性があるといったことですね。だけど、この品質をこの値段にすれば、買う側は喜んで買うでしょうという、幸福感に偏りを持たせてしまっているということで。
小林:僕が思っているRitaのSenseというのは、そういう買う側だけのバランスではないこと。もう世の中でたくさん言われだしていることではあるけれども、そういうSenseですよね。
皆川:そうですね。
小林:最近はそういった問題がファッションの業界でもいろいろ出てきていますよね。特に中国のウイグル問題。実際のところがどうなっているのか調べてみると、一部ではジェノサイド(虐殺)が言われています。一方では中国側がウイグル地区は安全で平和だとアピールするミュージカルみたいな宣伝ツールを作ったりもしているでしょう。あれは、皆川さんはどういうふうに見ているんですか?
皆川:明らかに値段のバランスが崩れているときには、価格というのは労働から決まってくることがあるので、その価格で出るということは、労働にどこか問題が起こっているんだろうなと。
小林:というのは僕も思っています。
皆川:そのうえで、そういうものが今かなりスタンダードなプライスになってしまっているという危険性があるんです。こういうものはこのくらいの値段で買えるものだと思われている価格というのはすごく低い状態にある。
そして、もし人がそういった低価格のものが孕んでいる危険性を知らずに買ってしまうとすれば、そこにある劣悪な労働環境や搾取の状況を結果として容認しているということになってしまいます。
巨大な企業がそういうことをやっているケースが多いので、かなり隠すということにも長けているなと感じるんですけど。巨大企業は国とも関わりがあるでしょうし、そこは深刻ですけど……。
なので、こういったことを声高に「暴く」みたいなことじゃないとしても、個人個人の意識としてもっと関心を持ちましょうというふうに振り向けていくことは必要かなと思ってます。
物の値段と労働は結びついているから、値段から原材料の価値を引くと、他にも細かいものはあるとしても概ねは労働工賃なわけです。あるTシャツが仮に1,000円だとします。もしそれを自分で材料を買ってきて縫うのだとしたら自分の工賃はいくらになるだろうか。もしかしたら材料の布自体もその値段では買えないということもあるかもしれない。だとすると、その布はどういう労働環境で綿が作られているのかというふうに、どんどん紐解いていく。そういう「価格の意味」みたいなことを観察したり想像してみることが大事なんだと思います。そうすれば現在は理解するのが難しいほどの値段がスタンダードになりつつあることがわかると思います。
小林:カシミヤのセーターが2,000円とか普通はあり得ないですよね。
皆川:あり得ないですね。それが単に「安価で良かったね」と言う時代が、ファストファッションで20~30年はあったわけです。さすがにそれは買う側が「良かったね」だけでは、今までの地球環境が壊れていくのと同じ道理になってしまう。
小林:サステナビリティ=想像力だというのがわかりますね。
皆川:本当にそう思います。
小林:想像することをやめちゃうと、続いていくというイメージにつながっていかないですよね。もっと言えば「進化」って、この対談の中でも何度も出てくるんですけれども、せめぎ合って「無理だったね」と言って終わるのではあまりにももったない。進化ということからすれば、僕らはそんなことのためにここに存在しているわけじゃない感じがどうしてもするから。ここのところ、そういう傾向がすごく強くなってきています。
皆川:まさにRitaの目線で想像してみたときには「これを作るには、こういう仕事やこういう経験があって、こういう形までたどり着いたんですよね」という想像がつく。そうすれば「これを作ってくれてありがとう」と思って大事にしようと思う。自分が労働から得たお金のこのぐらいをこのモノに費やしてもいいんだとしっかり納得ができる。「安いからうれしかった」じゃなくて、自分はこのモノを買うときに、この人の仕事や経験やこの材料に対しての敬意としてお金を払っているんだという意識が本当に想像できたら、変わるんだと思うんです。
インフレ/デフレということだったり、「普通、これってこのぐらいだよね」ということもなくなって、もっと自由な、人間の感情とか生活に根差した経済ができるんじゃないかなと思うんですけど。
今、商品は大体フォーマットにはまっているから、これは大体いくらぐらいとか決まっているようだけれど、その背景を、作ったほうも伝えることが大事だと思います。分かっていれば、同じものでもまったく違う値段が付いていてもよくて、それが自由な経済になるんじゃないかと思います。
小林:もちろんそれは自由といってもデタラメでいいということではなくて、そこでいろんな工夫をしていかなければいけないわけですよね。そういう意味での仕組みづくりというのは非常に大事だなと思っています。
僕らは木更津市と共同でイノシシなど獣害として捕獲された動物を解体処理する施設を運営しているんです。そこで処理された肉はもちろんソーセージなどに活用してきているんですが、同時に骨も大量に出るわけです。去年の実績だけでいっても1,500kgくらいかな? これがいわゆる「産業廃棄物」になってしまうということを聞いて。
皆川:燃やしちゃうんですか?
小林:大体はそうみたいです。なので、僕らはその骨でスープを作るということを考えて初めてます。そうするとスープにとっての適正な原価が出てくる。
皆川:材料の歩留まりが上がっていけばそれぞれの原価が下がる。
小林:ええ。そういうことが、あまり大きな仕組みの中じゃなくできればいいなと。というのも、僕らは一生イノシシの骨と付き合いたいと思っていても、他の人がそこに気づいて競争になるかもしれないし。そうしたらその都度またいろいろと考えて変えながらまた新しい原価のあり方みたいなものを見つけていくしかないんだろうなと。そこを無理に取りに行くと、あまり良くないものになっていくだろうし。
そんなことをここのところ想像していたんです。だから僕は「Rita」だけでなく「流動性」であると投げ掛けているんですけれども。
もしそれを「文化」という範疇まで広げて言うならば、今問題になっている日本と韓国の問題とか、台湾とか中国とか、いろいろあるけど、それぞれが隣り合うなかで培ってきたいろんな文化、食における豊かさみたいなことをはじめとして、みんなじつはすごく通じ合えるものって持っているでしょう。それは命を奪い合うんじゃなくて、分け与えていくという、シェアするようなところから生まれてきた喜びや美しさと言ってもいいかもしれないから。
皆川:「流動性」ってつまりは執着しないということじゃないですか。執着して流動性がなくなった時点で、さきほどの「奪い合うシェア」になっていってしまう。自分たちはそこに執着しないで離れて違う価値をまた見つけて、という流動性を持つということは「Ritaと流動性」は、つながりとしてはとても理にかなっているなと思います。
小林:そうですよね。困難なことがあるところにこそ僕らもう少し想像力を持ってもっとつながっていくべきで。そうすると、そこにまた新しいポジティブな種があったりするから。みんなが「これいけるわ」みたいなところにだけ集まって奪い合うというサイクルにあまり行かずにね。
「場の意味」を感じられる、体験する宿
小林:そしていまちょうどKURKKU FIELDS(以下KF)では<COCOON>という宿泊施設のプロジェクトを皆川さんにお願いしているところで。
僕がこれを皆川さんにお願いしようと決めたのは、ちょっとした勘のようなものでした。僕が最初に皆川さんにお会いして、そこからお付き合いが始まってより強く感じていたことなんですが、皆川さんの独特の所作みたいなもの、モノを通したりモノを介したりする感覚や所作が、とてもステキだなとずっと思っていて。
皆川:ありがとうございます。
小林:皆川さんが作られているモノからもなんとなくそういったところは感じていたんですが、もし宿泊施設であればそのモノを通してだけじゃなく、時間の中でそれを経験してもらうことになる。それならば皆川さんにお願いできるんじゃないか。それが一番いいことだと思った。僕より絶対そういうところが優れている人じゃないかと思ったということです。
皆川:僕自身も以前から「能動的な宿」をやりたいなとずっと考えていて。数年前の展覧会にもいつかやりたいこととして書いていたんですけど、いわゆる宿に泊まってそこで何か贅沢なサービスとか設えを楽しむというのではなくて、そこに泊まることで自分たちでなにか体験をしたり、日常的ではないものが感じられたり。それが比較的簡素な状況でやることができたら、いろんな世代の人が来られたりしていいなと思っていたんです。
小林:素敵ですね。
皆川:で、ここに来させていただいていろいろ見てみると、ここではいろんなものを作られていて。野菜から、チーズやソーセージとか。ここに泊まってそれが体験できたら素晴らしいなと思って。それこそ泊まることの意味だなと思ったんです。だとすれば、部屋自体は比較的簡素でもいいじゃないか、と。
宿というのは、そこに物質的に、空間的にくつろげるということだけが価値じゃなくて、そこに来たことの意味を咀嚼できたり、思考できるような場に意味がある。そんな「場の意味」を感じられるような宿があっていいなと思ったんです。
小林:僕らは以前から「オーバーナイト」という言い方をよくしていたんですけど、昼間だけじゃなく夜をまたいでの早朝とか夜も含めて感じられるものってすごく大事に思う気持ちがあって。それが、「彷徨う」ような過ごし方のなかで時間をどう活かすことができるか。
皆川:ええ。今まさに進んでいるこのプロジェクト、だんだん煮詰まってきていますけど、これからいろいろ運営の方法を考えていく段階なんだと思うんですね。で、その運営というのは第一にこの「体験」がしやすい形を作っていくことになるんだと思っています。それは「サービス」ということでもなくて、もっと「整えていく」というような感覚ですかね。「サービス」という言葉が悪いわけじゃないんだけど、それを感じさせないような仕組みがここでは居心地が良いんじゃないかなと思ってます。
小林:はい、すごく楽しみです。では今日はどうもありがとうございました。
皆川:ありがとうございました。
対談を終えて
とにかくいつも笑顔で接してくださる人です。
だけど言うことは言う。
その指摘ももちろんといってよいほど、的を得ていたり、鋭かったりするのです。
その上に、もう一度「だけど」と言わせてもらいますが、
笑顔でいろんな問題や、それらに対しての意識も明確に感じたうえで、
(おそらく)やっぱり笑顔なのです。
本当に、始まりから最後までというか、掛け値なしで笑顔でいられる(いてくれる?)
僕にとって数少ない、そういった個性を持った人なんです。
この対談中も全くその佇まいでありました。
これからもよろしくお願いいたします。
小林 武史
PROFILE皆川 明
デザイナー。手作業による図案でのオリジナルファブリックを主軸としたものづくりで知られるブランドminä perhonen(ミナ ペルホネン )の創設者、デザイナー。個人での活動として、新聞などへの挿画や、海外のテキスタイルブランド及びテーブルウェアブランドへのデザイン提供、宿のディレクション等も手がけている。主な展覧会に、「ミナ ペルホネン / 皆川明 つづく」(東京都現代美術館、兵庫県立美術館)がある。
minä perhonen
https://www.mina-perhonen.jp/